
1.京都府の相続税申告の状況
京都府の令和3年度における相続税の申告件数は3,860件、そのうち相続税がかかった課税件数は3,007件です。
課税割合は10.62%で全国5位、相続1件あたりの納付税額は約1,698万円で全国8位となっています。
全国平均は、課税割合は9.33%、相続1件あたりの納付税額の平均は約1,820万円であることから、課税割合は全国平均を上回り、納付税額は若干下回っていますが、全国平均に関しては東京都の数値が突出して高いため、このような数値になっているのであって、京都府も十分に高いといえます。
関西地区で見ると、大阪9.45%、滋賀8.50%、奈良10.01%、兵庫9.84%、和歌山7.46%の中で京都府は最も高い割合となっています。
京都府の課税割合の特徴は、全国平均並みのエリアが少ないことです。高いか低いかに二極化しています。
京都府は古くから残る寺社などが多く、景観保全のために高層マンションなどの建設ができない地域があります。そのような地域で持ち家に居住している人は戸建てになる可能性が高く、さらに富裕層である可能性も高くなります。
さらに、京都府は言わずと知れた日本を代表する観光地であり、府内各所に観光名所があります。これら観光地の地価は下がりにくく、市街地化している地域では強い上昇傾向によって高額な地価を誇っているため、全国でも相続税が課税されやすい地域となっているのです。
2020年からの新型コロナウイルスの影響によって、京都府の地価も軒並み打撃を受けていますが、それでも「都道府県庁所在地の最高路線価ランキング」では全国6位の順位を守っています(※)。
特に、宿泊事業を行っている事業者の場合、宿泊施設への課税や、高価な美術品や骨董品へ課税が高額になりやすく、事業の継承時に多額の相続税が発生する可能性が高くなるため注意しなければなりません。
2.京都府の各エリア毎の相続税データ
令和3年度の税務署管轄エリア毎の相続税データを掲載します。
| 税務署名 | 管轄地域 | 申告 件数 | 課税 件数 | 1件当り 納付税額 (万円) | 申告割合 | 課税割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上京 | 北区 上京区 | 434 | 339 | 1,603 | 19.85% | 15.51% |
| 左京 | 左京区 | 385 | 292 | 2,691 | 22.66% | 17.19% |
| 中京 | 中京区 | 251 | 178 | 2,740 | 23.57% | 16.71% |
| 東山 | 東山区 山科区 | 258 | 199 | 1,709 | 12.48% | 9.63% |
| 下京 | 下京区 南区 | 322 | 254 | 1,784 | 17.22% | 13.58% |
| 右京 | 右京区 西京区 向日市 長岡京市 大山崎町 | 776 | 584 | 1,664 | 15.32% | 11.53% |
| 伏見 | 伏見区 | 354 | 283 | 1,879 | 11.39% | 9.10% |
| 福知山 | 福知山市 綾部市 | 108 | 97 | 1,002 | 6.93% | 6.23% |
| 舞鶴 | 舞鶴市 | 80 | 70 | 1,593 | 7.37% | 6.45% |
| 宇治 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久御山町 井手町 宇治田原町 笠置町 和束町 精華町 南山城村 | 680 | 532 | 1,135 | 12.56% | 9.82% |
| 宮津 | 宮津市 伊根町 与謝野町 | 32 | 30 | 840 | 4.80% | 4.50% |
| 園部 | 亀岡市 南丹市 京丹波町 | 136 | 111 | 1,173 | 8.22% | 6.71% |
| 峰山 | 京丹後市 | 44 | 38 | 639 | 5.02% | 4.34% |
| 京都府計 | 3,860 | 3,007 | 1,698 | 13.63% | 10.62% |
それでは、エリアそれぞれの特徴を課税割合の高い順に解説していきます。
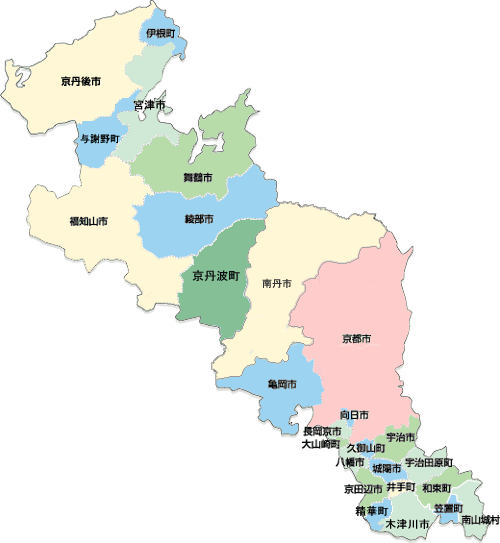
【出典サイト】府内市町村・官公庁・都道府県等|京都府HP
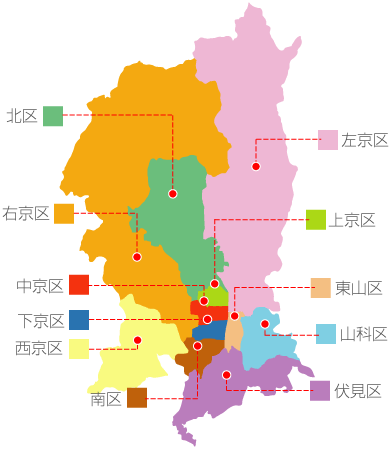
京都市:京都市のあらまし(行政区)|京都市情報館
(1)左京区
京都市の左京(さきょう)区は、京都市の北東部に位置し、滋賀県とも隣接しています。
銀閣寺、平安神宮、比叡山などの名所や、名門の京都大学など多くの有名な大学のキャンパスが点在し、自然の豊かな山間部も存在しており、そのバランスのとれた魅力があります。歴史的かつ自然豊かな街並みは、環境の良いベッドタウンとして非常に需要があります。
課税割合は17.19%で京都府内トップです。相続1件あたりの納付税額も2,691万円と京都府内2位の高さです。
中京区の地価は、1平米あたり26万円程度で、京都市内も6番目に高い水準となっています。また、岩倉地区などが市街地化調整区に指定されているため、大型マンションの建設が制限され、持ち家率が比較的高い地域となっています。さらに、ベッドタウンとして多くの居住者が住むことから、高い課税割合が維持されていると考えられます。
(2)中京区
中京(なかぎょう)区は、京都市の中央南部に位置する小さな区で、かつて平安京が存在し、道路が碁盤の目のように整備された歴史的なエリアです。
四条通周辺には京都市役所、金融機関、オフィスビル、商業施設などが集中しており、京都市の行政と産業・経済の中心地として機能しています。また、北部には二条城があり、南部は住宅地として落ち着いた雰囲気のエリアです。
課税割合は16.71%。相続1件あたりの納付税額は約2,740万円と京都府内トップです。
中京区の地価は1平米あたり165万円と、京都市内で2番目に高額です。そのため不動産の評価額が高額になりすく、このような高い結果となっています。
(3)上京区・北区
上京税務署エリアは北区と上京区からなり、京都市の中央に位置しています。
北区は京都市内で3番目に広い区で、京都市全体の約10%を占めています。このエリアには金閣寺や大徳寺など多くの有名な観光名所が点在し、山岳地帯も広がっているため、歴史と自然が調和した住宅地が存在しています。
一方、上京区は非常にコンパクトなエリアで、面積はわずか7.11㎢しかありませんが、京都府庁や迎賓館など行政機関が集中しています。さらに、国宝である「相国寺」など歴史的な建造物も多く、古くから行政の中心地としての役割を果たしています。
上京エリアの課税割合は15.51%で、相続1件あたりの納付税額は約1,603万円となっています。課税割合は3番目に高い位置にありますが、相続税の納付税額は13エリア中7番目に過ぎません。
1平米あたりの地価に関しては、北区が約27万円、上京区が53万円となっており、上京区が約2倍の高さです。どちらも京都府全体と比較したら高額な地価ですが、上京区は非常に小さなエリアで、観光スポットが集中しているため、住宅地においても希少価値が高く、地価や家賃が非常に高くなっています。
このエリアはアクセスが便利で、富裕層や現役世代の方々も多く住んでいると考えられます。
(4)下京区・南区
下京エリアはその名称通り、京都市の南部に位置している下京区と南区からなります。
下京区には京都府の中心駅である京都駅があり、周辺には多くの商業施設が建設されています。四条通りには四条河原町と呼ばれる京都でも有名な繁華街が広がり、市内の賑わいの中心となっています。
南区は産業振興拠点地区が広がり、大手企業である任天堂やSGホールディングスなどが本社を構えている地域です。そのため、周辺の住宅地には高所得者が多いと考えられます。
課税割合は13.58%で、相続1件あたりの納付税額は約1,784万円となっています。
地価に関して、下京区は1平米あたり194万円と非常に高額で、京都市内で最も高い地価です。京都駅をはじめとして京都市の中心施設を含んでいるからです。
南区の地価は1平米あたり25万円で、京都市内では7位に位置しています。南区の地価がやや低めであることが、全体の平均値を下げている要因と考えられます。
(5)右京区・西京区エリア
5位は右京区・西京区エリアで、右京区、西京区、向日市、長岡京市、大山崎町からなり、京都市の西部から西南部に広がるエリアです。
このエリアは広大な面積を持ち、主要都市へのアクセスが優れているため、ほぼ全域がベッドタウンとして発展しています。特に右京区の南部は、歴史的な住宅地であり、皇族の別荘地などが点在しています。この地域は高い地価が特徴です。
課税割合は11.53%で、相続1件あたりの納付税額は約1,664万円となっています。
地価に関しては、府内で1位から4位までを占めています。全体がベッドタウンとして発展しているため、高い課税割合と地価は当然の結果といえます。
これまで説明した5つのエリアは、京都府全体の課税割合平均を上回っています。すべてが京都市内に位置し、観光地の地価が高いことから相続税の高課税につながっています。富裕層の他に宿泊事業を営んでいる事業者からの相続税の納税も多くなっています。
次のセクションでは、京都府の課税割合平均を下回るエリアに焦点を当てて解説します。
(6)宇治エリア
宇治エリアは、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村の、府内最も多くの市町村からなるエリアです。
「宇治」と聞くと多くの人が「宇治抹茶」を思い浮かべるのではないでしょうか。宇治は美味しい抹茶の代名詞として知られ、全国で最も多くのてん茶を生産する地域で、その生産量は全国の2割以上にも及びます。
このエリアは自然に囲まれた田舎町で、京都市内では感じられないのんびりとした雰囲気があります。にもかかわらず、京都市へのアクセスが良く、ベッドタウンとしての需要が高い地域でもあり、特に京田辺市は再開発が進行中で、人口が着実に増加しています。
課税割合は9.82%と、京都府の平均値を下回りますが、全国平均の9.33%を上回っています。このエリアは京都市への通勤率が高く、高所得者が多いためと考えられます。
相続1件あたりの納付税額は約1,135万円となっています。地価は、京都市内の半分程度であり、不動産による課税はされにくいです。不動産課税よりも、預金などの相続財産に注意が必要なエリアです。
(7)東山区・山科区
東山区と山科(やましな)区からなる東山エリアは、京都市の南東部、左京区の南部に隣接しています。
東山区は、祇園や三条京阪などの繁華街が形成され、早くから市街地化している地域です。美しい歴史的建造物が多く現存しており、その街並みを保護するために再開発の制約が非常に厳格で、住宅地の拡大が制限されています。そのため、人口は市内で最も少なく、高齢者の比率が最も高い区となっています。
山科区は、京都市や大阪府のベッドタウンとして発展しているエリアで、もともと山間部にある農村地域でした。自然環境が豊かで落ち着いた雰囲気がありますが、地価は低い傾向がありました。しかし、ベッドタウンの需要が増加し、地価も上昇しています。
課税割合は9.63%で、宇治エリアと同様の水準ですが、相続1件あたりの納付税額は約1,709万円と、宇治エリアより多くなっています。
東山区の地価は1平米あたり85万円と非常に高額で、京都市内では下京区と中京区に次ぐ3位ですが、住宅地が限られていることから、相続税の発生は多くはないと考えられます。
そのため、ベッドタウンである山科区が相続税の中心となり、その地価は市内で最も低く、1平米あたり15万円という低額な地価であるにもかかわらず、高い納付税額につながっていると考えられます。
(8)伏見区
伏見区は、京都市の南部に位置しており、東西に細長い形をしています。伏見港などを中心に古くから水運の拠点として発展してきました。
市街地に近いことからベッドタウンとしても注目され、現在では市内で最も多い人口を擁する区となっています。
課税割合は9.10%で全国平均を下回りますが、13エリア中8位でもこの水準です。また、相続1件あたりの納付税額は約1,879万円となっており、府内3位である点には十分注意しなければなりません。
伏見区の地価は京都市内11区中10位と順位は低いですが、1平米あたりは17万円で府内3位の向日市に次ぐ金額となっています。
ベッドタウンであり、さらに人口が多いことから相続税が発生しやすいこと、市街地への通勤者が多く所得が高額になりやすいことが影響していると考えられます。
(9)その他のエリア
京都府は課税割合の2極化が特徴と前述した通り、伏見区の次からは一気に課税割合が落ちます。ひと言でいうなら「田舎」エリアがまとまっています。
| 税務署名 | 管轄地域 | 1件当り 納付税額 (万円) | 課税割合 |
|---|---|---|---|
| 園部 | 亀岡市 南丹市 京丹波町 | 1,173 | 6.71% |
| 舞鶴 | 舞鶴市 | 1,593 | 6.45% |
| 福知山 | 福知山市 綾部市 | 1,002 | 6.23% |
| 宮津 | 宮津市 伊根町 与謝野町 | 840 | 4.50% |
| 峰山 | 京丹後市 | 639 | 4.34% |
課税割合は4~6%台となり、相続1件あたりの納付税額も1,000万円程度もしくは未満となります。
ただ1点、舞鶴エリアだけは、納付税額1,593万円と少し高めです。
亀岡市、南丹市、京丹波町ならなる園部エリアは、京都府の中央部に位置しています。
農業が伝統的に行われており、黒豆や松茸、栗は全国的に知られている特産品です。また、製造業も盛んで、特に亀岡市が経済の中心地となっています。
京都市の北部と西部に隣接しているにも関わらず地価が低いことから、京都市のベッドタウンとして急成長を遂げています。
車社会であるため流入しているのは若い子育て世代が中心であり、相続税の発生率は低くなっているようですが、地価は上昇傾向にあるため、広大な農地を所有している高齢者などは注意が必要なエリアといえるでしょう。
3.京都府の税理士情報
京都府の税理士は近畿税理士会(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)に所属しており、その会員数は15,320人(令和5年9月末現在)です。
そのうち京都府にいる税理士は1,895人(平成30年3月31日現在 日本税理士会連合会 平成30年5月発行税理士界)で、近畿税理士会に所属する税理士の1割強ということになります。近畿2府4県のうち、京都府が最も相続税が起こりやすいにもかかわらず少ないように思います。
京都府の令和元年における相続税の申告件数は3,860件であったことから、1件当たり0.49人の税理士しかいないということになります。
さらに、前述の通り相続税の中心は京都市内であることから、1,000人を超える税理士は京都市内に在籍しています。その中でも、中京区には407人、下京区には268人が在籍しており、京都市の税理士の半数以上がこの2区に集中しています。
そのため、京都府内で税理士を探す場合は、どのエリアに居住していたとしても、京都市でも税理士を探した方が、より良い出会いにつながる可能性が高いでしょう。
なお、京都府の中央より北部の場合には、兵庫県や福井県の税理士も探してみることをおすすめします。同様に、京都市から離れた京都府南部では、大阪府、奈良県、滋賀県の税理士も候補にしましょう。
相続税では土地の評価に強い税理士を見つけることが重要になります。特に田舎エリアになると、市街地や住宅地、山間部など、さまざまな種類の土地を所有している可能性があるため、そのエリア事情に精通した知識を持っている税理士が適任です。
無理に遠い京都市に出て行くよりも近い他県の方が、そのような税理士を見つけやすいでしょう。
また宿泊事業を営んでいる人の多い京都府では、高価な美術品や骨董品を代々相続している可能性が高いです。物によっては土地など遥かに超える金額になる場合もあるため、美術品や骨董品が多い場合には、こうした評価に強いことも税理士を選ぶ基準にしましょう。
不動産のみに気を取られず、自分の相続に合った能力を持つ、相続に強い税理士を探すことが重要です。
当サイトでは京都府の税理士のみならず、隣県の税理士も簡単に検索できるようになっています。もちろん、相続税に精通した相続に強い税理士のみをご紹介しております。
良い税理士探しのお手伝いができれば幸いです。
【参考サイト】「税理士登録者数 」| 日本税理士会連合会、「近畿税理士会とは:近畿税理士会のご案内」│近畿税理士会







