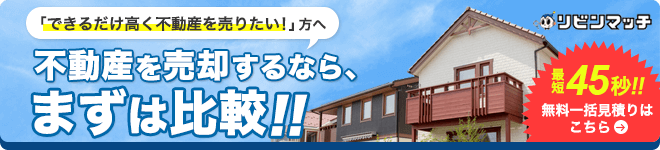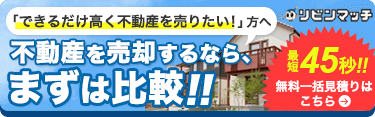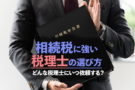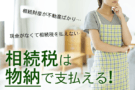タワーマンションの固定資産税改正は相続評価額に影響するのか?

首都圏を中心に人気の衰えないタワーマンションですが、2017年の税制改正によりタワーマンションにかかる固定資産税額の計算方法の見直しが行われました。この計算方法の見直しは、タワーマンションの高層階の固定資産税を増税し、低層階を減税するというものです。
この改正は、タワーマンションにかかる相続税の計算に影響するかどうか、タワーマンションを保有する人たちにとっては心配事の1つではないでしょうか。
今回は、「タワーマンションにかかる固定資産税額の計算方法の見直しが、相続税の計算に与える影響」についてご紹介します。
目次
1.タワーマンションの固定資産税改正のポイント
初めに、2017年に行われたタワーマンションの固定資産税額の改正についてご紹介します。この改正は、タワーマンションの固定資産税額の「計算方法」を見直す改正です。
1-1.改正のポイント
対象は2017年4月以降に売買契約した「居住用超高層建築物」
「居住用超高層建築物」とはタワーマンションのことを言い、建築基準法に規定されている高さ60m以上で、複数の階に人が居住できる建物のことです。高さ60mのマンションは一般的に20階建て以上が該当します。
2017年4月以降に売買契約したタワーマンションが対象になりますので、それ以前に購入したタワーマンションについては以前の固定資産税額の計算方法によって算出されます。
高層階は増税!低層階は減税!
タワーマンションの高層階の固定資産税を増税して、低層階を減税する調整計算が行われます。
以前の固定資産税額の計算は、階層は考慮されておらず、マンション全体の固定資産税額を部屋の所有者の専有面積により按分計算し、各人の固定資産税額を算出していました。高層階の販売価格が高い部屋と、低層階の販売価格が安い部屋の固定資産税の負担額が同じだったのです。
しかし、この改正により、資産価値に応じて固定資産税の負担を公平にすることができるようになりました。これは、あくまでも各所有者の固定資産税の負担額の改正ですので、タワーマンション全体の固定資産税額は変わらず、増税にも減税にもなりません。
各人の固定資産税額は、補正率を使って算出されます。補正率は、「1階を100とし、階が1階上がる毎に10/39を加えた数値」となっています。
つまり、以下の計算式で算出できます。
N階の補正率
10/39 ×(N-1)+ 100
具体的な計算は、以下のようになります。(便宜上、3階建てで計算)
| 1階の補正率 | 10/39×(1-1)+ 100 | 100% |
| 2階の補正率 | 10/39 ×(2 - 1)+ 100 | 102.5% |
| 3階の補正率 | 10/39 ×(3-1)+ 100 | 105.1% |
| 1~3階までの合計 | 100% + 102.5% + 105.1% | 307.6% |
この補正率でタワーマンション全体の固定資産税を按分していきます。
タワーマンション全体の固定資産税が20万円とすると、
| 1階の固定資産税 | 20万円×100/307.6 | 65,020円 |
| 2階の固定資産税 | 20万円×102.5/307.6 | 66,644円 |
| 3階の固定資産税 | 20万円×105.1/307.6 | 68,335円 |
となり、階数によって固定資産税額の負担が変わり、高層階は固定資産税の負担増、低層階は固定資産税の負担減となります。
1-2.マンションと一戸建ての固定資産税評価額の違いとは?
タワーマンションの固定資産税額の計算式をご紹介しました。この固定資産税は各市町村が算出する固定資産税評価額によって算出されます。
では、マンションと一戸建ての家の固定資産税評価額はどのような違いがあるのでしょうか。
一戸建ての固定資産税評価額
一戸建ての固定資産税評価額は、土地と家屋に分類されます。
土地については、各市町村によって定められた「固定資産税路線価」によって各市町村の固定資産税課が算出します。固定資産税路線価は、公示地価の70%と言われています。
一方、家屋は再構築に必要な費用から建物の劣化などによる減価を差引いた額が評価額となります。この算式で算出される家屋の固定資産税評価額は実際の市場価格より安くなる場合が多く、だいたい市場の6割程度と言われています。
マンションの固定資産税評価額
マンションの固定資産税評価額の計算は、基本的には一戸建ての固定資産評価額と同じように算出されます。
しかし、分譲マンションでは各部屋の所有者が違うので、土地・家屋ともに按分計算が必要です。按分計算は、通常、その所有者の専有面積により計算されます。
2.タワーマンションの固定資産税評価額の改正は相続税に影響あるの?
人気の高いタワーマンションですが、相続税対策としても人気があります。一般的には「タワーマンション節税」と言われる手法を使った節税方法です。相続税の対象になる人が、タワーマンションを購入することで相続財産を減らすことができるのです。
今回の改正は「タワーマンション節税」にどのような影響を与えるのでしょうか。
2-1.「タワーマンション節税」とは?
相続税の計算は、被相続人(亡くなった方)の全財産を評価していきます。現金を保有している場合は、その現金の額そのものが相続評価額となりますが、マンションなどの不動産を購入した場合は、現金で保有しているよりも格段に相続評価額を減額することができます。
この節税方法で最適な不動産が、タワーマンションの高層階です。タワーマンションの高層階は、実際の取引価格と相続評価額に大きな差があり、一般のマンションを購入するより節税効果に優れています。
節税効果に優れている点をいくつかご紹介します。
土地の評価額が低くなる
タワーマンションは部屋数が多いため、自ずと各部屋の土地の専有面積が少なくなります。そのため、土地の評価額を低く抑えることができます。
販売価格と相続税評価額の差が大きくなる
高層階は、人気が高く、販売価格が落ちることがなかなかありません。家屋の相続評価額は固定資産税評価額(再構築に必要な費用から建物の劣化などによる減価を差引いた額)により計算されるため、その分、実際の取引価格と相続評価額の差が大きくなります。
換金性に優れている
前述した通り、人気のあるタワーマンションの高層階は中古市場でも値崩れが起きにくく、売却が容易です。
投資物件として優れている
高層階は、賃貸としても人気があり、投資物件としての価値も高いです。
2-2. 今回の改正は、「タワーマンション節税」に影響しない!
「タワーマンション節税」の節税効果についてご紹介しましたが、今回の「タワーマンションの固定資産税の改正」が「タワーマンション節税」に影響を与えるのか気になる点だと思います。
現在のところ、この改正による相続評価額に影響は全くありません。今まで通りに「タワーマンション節税」の手法を使うことは可能です。
なぜなら、「タワーマンションの固定資産税の改正」は、あくまでも税額計算の見直しであり、固定資産税評価額については特に改正されていないからです。
しかし、国税庁は「タワーマンション節税」について問題視している動きがありますので、今後「タワーマンション節税」を規制するような税制改正が行われる可能性があります。
また、平成27年に国税庁が行った記者発表で「財産基本通達6項の運用を行いたい。」と見解を示しています。
財産基本通達6項とは、「著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する。」というもので、国税庁で相続評価額を決定できるものです。つまり、タワーマンションの相続評価額の計算に、固定資産税評価額が使用できない場合が出てくるということになります。
3.「タワーマンション節税」をする際の注意点
相続税の節税効果が高い「タワーマンション節税」ですが、税務調査で否認されるケースも多々あります。節税はあくまでも手段であって、目的になってはいけません。タワーマンションの購入が「節税目的」とされた場合はタワーマンションの相続評価額は否認され、購入価格を相続評価額として相続税が課税されてしまいます。
調査で否認されないためには、どのような点を注意すればよいのでしょうか。いくつかご紹介したいと思います。
3-1.タワーマンション購入時の被相続人の意思能力
被相続人(亡くなった方)がタワーマンション購入時に、意思能力があるかどうかが重要な判断ポイントとなります。本人の意思能力がない状態でタワーマンションを購入すると、家族による租税回避行為となり否認されてしまいます。意思能力がなくなってからの相続対策は打つ手がなくなってしまいます。早め早めの対策が必要です。
3-2.相続後すぐに売却しない
タワーマンションを相続後すぐに売却すると、税務署から租税回避行為の疑いを持たれます。税務署では不動産の登記情報を調査しているので、売却するとすぐ分かります。相続税の調査は通常、申告から1~2年後に行われることが多いので、出来るだけ長く所有、利用することが望ましいです。
3-3.購入目的を明確にする
タワーマンションの購入目的をはっきりさせておいた方がいいでしょう。例えば、「相続された家族の住まいに利用する」や「投資物件としての購入」など、租税回避行為ではないことを明確にしてきましょう。また、購入目的通りに運用することも大切です。
まとめ
今回は、「タワーマンションの固定資産税改正による相続評価額の影響」についてご紹介しました。この改正によって「タワーマンション節税」に直接的には影響はありません。
しかし、国税庁も問題視している節税方法ですので、いつ新たな税制改正により規制されるか分かりません。これからの動向を気をつけて注目していく必要がありそうです。