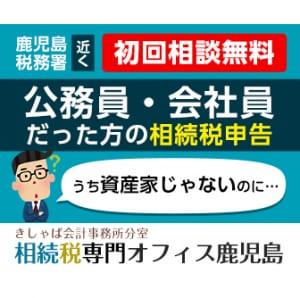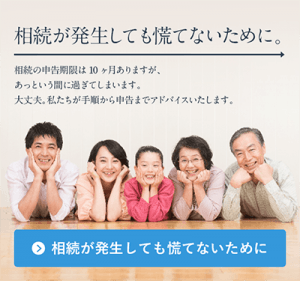鹿児島県の概要
鹿児島といえば「豚」と連想する人が多いのではないでしょうか。実際、養豚は鹿児島県の基幹産業となっており、豚の出荷頭数は日本1位にもなっています。そのほか、鹿児島県と言えば芋焼酎や、さつま揚げ等が美味しい地域としても知られています。
世界遺産の屋久島があるのは鹿児島県で、種子島や新島等の離島がある都道府県としても知られており、桜島の噴火も有名です。こうした自然や文化に非常に恵まれており、観光面でも需要が高い地域となっています。

鹿児島県は大きく7つの地域に分類することができます。まずは鹿児島市を中心とする「鹿児島地域」です。そのほか、薩摩半島に位置する「南薩地域」、その北部に位置する「北薩地域」、県中央部に位置する「姶良・伊佐地域」、大隅半島に位置する「大隅地域」、種子島に位置する「熊毛地域」、奄美や大島によって構成される「大島地域」です。
鹿児島県の人口は県全体で140万人ほどおり、約60万人が鹿児島市に住んでいます。また鹿屋市や霧島市等は10万人以上が住んでおり、県内は比較的どこも栄えています。なお、合計特殊出生率は1.63であり、全国でもトップクラスの高さです。ただし、高齢化が早い地域でもあり、財政改革が必要な地域です。
こうした特徴をもつ鹿児島県の相続税事情について見ておきましょう。
鹿児島県は課税発生件数・課税割合のどちらも低い
熊本国税局発表の令和3年度の都道府県別相続税課税状況をみると、鹿児島県は課税発生件数と課税割合が全国的に低めであることがわかります。
課税発生件数は790件で、課税割合(死亡者のうち課税された割合)は3.59%と全国45位です。全国平均は9.33%ですので、非常に低い割合であることがわかります。
また、鹿児島県の被相続人1人当たりの相続税納付額は約983万円で、こちらは全国で39番目となっています。つまり、鹿児島全体の相続税の特徴は課税発生件数も少なく、仮に相続税が発生しても税額は少ないことがわかります。
エリア別の相続税の課税状況
鹿児島県内の税務署エリア別の令和3年度相続税データです。
| 税務署名 | 管轄地域 | 申告 件数 | 課税 件数 | 1件当り 納付税額 (万円) | 申告割合 | 課税割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 鹿児島市 三島村 十島村 | 530 | 395 | 998 | 8.31% | 6.19% |
| 川内 | 薩摩川内市 さつま町 | 55 | 44 | 1,173 | 3.41% | 2.73% |
| 鹿屋 | 鹿屋市 垂水市 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 | 80 | 65 | 2,048 | 3.27% | 2.66% |
| 大島 | 奄美市 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町 | 36 | 31 | 937 | 1.96% | 1.68% |
| 出水 | 阿久根市 出水市 長島町 | 48 | 44 | 435 | 3.77% | 3.46% |
| 指宿 | 指宿市 | 21 | 17 | 303 | 3.49% | 2.82% |
| 種子島 | 西之表市 中種子町 南種子町 屋久島町 | 9 | 7 | 170 | 1.40% | 1.09% |
| 知覧 | 枕崎市 南さつま市 南九州市 | 38 | 29 | 669 | 2.40% | 1.83% |
| 伊集院 | 日置市 いちき串木野市 | 33 | 27 | 745 | 3.12% | 2.55% |
| 加治木 | 霧島市 伊佐市 姶良市 湧水町 | 125 | 99 | 474 | 3.96% | 3.14% |
| 大隅 | 曽於市 志布志市 大崎町 | 38 | 32 | 1,775 | 2.74% | 2.31% |
| 鹿児島県計 | 1,013 | 790 | 983 | 4.61% | 3.59% |
鹿児島市で県内の半数が課税されている
鹿児島県内では、鹿児島市の課税発生件数が530件と特に多く、県内の半数以上を占めています。課税割合も6.19%と、県内平均3.59%を大きく上回っています。
ただし、1人当たり納税金額は998万円と県内平均額と同じくらいです。むしろ、鹿児島市よりも鹿島市や垂水市の方が高くなっています。
鹿児島市以外の課税割合はかなり低い
鹿児島市以外は、相続税がかかる割合はかなり低いです。高くでも3%代、低いエリアですと1%くらいです。ほとんど相続税が課税されることはないと考えて良いでしょう。
一方、被相続人1人当たりの相続税納税額でみると、鹿島市や垂水市では、2,048万円と全国平均よりも高い数値です。曽於市、志布志市も1,775万円と高いです。
相続税が課税される人は少ないですが、広大や土地を持っていたり、地元企業オーナーで評価額が高い自社株式を持っていたりすると、相続税が高くなる傾向がありますので、相続税対策は必須となります。
鹿児島県の税理士事務所はやや多い
鹿児島県の税理士事務所は県内に250以上あり、比較的多く事務所があることがわります。また1税務署あたり5名程度の従業員がおり、比較的税理士・スタッフも多いことが分かります。そのため、県内では税理士を見つけやすでしょう。
鹿児島市内では相続税事案が多いですが、その他のエリアではあまり多く発生していませんので、実際は相続税に慣れていない税理士も多いと考えられます。
相続税は納税額が大きく、土地の評価方法次第では大幅に減額できることもありますので、経験や知識がある税理士に依頼することが肝心です。