生命保険の種類と相続対策に有効な保険
生命保険と一口に言っても、生命保険には様々な種類と商品があります。何のために生命保険に加入するのか目的を明確にし、そ…[続きを読む]
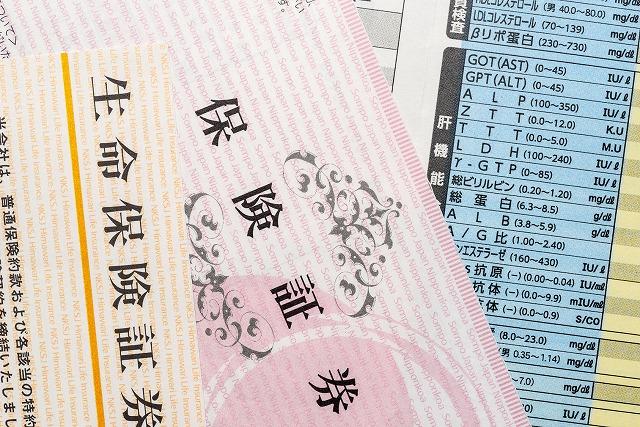
生命保険は誰でも比較的簡単に活用できる相続対策の1つです。計画的に賢く利用できれば、相続争いを防ぐことができ、更には、これまで積み上げてきた財産を無駄なく子や孫へ承継させることができます。
相続対策に生命保険を使う場合の知識を、契約パターンを用いながら完全解説します。
相続対策には大きく次の4つがあり、生命保険はいずれに対しても非常に有効な手段となります。
人はお金を目の前にすると、人格が変わってしまうことがあります。相続は多額の財産を分割するため、時として相続人間でトラブルを引き起こす場合があり、その意味を込めて「争続」と言われることもあります。
事前に生命保険を利用した対策を行っておけば、「争続」を防ぐことができるのです。
なぜ争続となるのか、それは相続人間で不公平感があるからです。
これを解決するために代償分割という制度があります。 代償分割では、多く受け取った相続人が、少なく受け取った相続人に対して現金を支払う必要がありますが、生命保険を利用することでその現金を死亡保険金で用意することができます。
決まった額の現金を、将来相続人となる特定の人に対して確実に渡したいという思いがある場合には、その人を死亡保険金の受取人とした生命保険を事前に契約しておくことで、その相続人に確実に現金を渡すことができます。
現金を遺した場合には遺留分の対象となり、遺留分侵害額請求を受ける可能性がありますが、死亡保険金は遺留分の対象になりませんので、渡したかった全額を渡すことができます。
死亡保険金には、残された家族の生活を守るためという意味合いもあることから、相続税の基礎控除枠とは別に、次の非課税枠が設けられています。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合には1,500万円となり、この金額までは相続税ゼロで保険金を受け取ることができます。
ただし、これは受取人が相続人である場合に限り適用されます。相続人以外の人が受取人として指定されている場合には適用できませんので注意しましょう。
納税は基本的に現金一括払いです。税額が大きくなる場合が多い相続税であってもそれは変わりません。
被相続人の財産で納めれば良いと思うかもしれませんが、遺産の多くは遺産分割が終わらないと利用することができませんので、それをあてにするのは危険です。
そこで死亡保険金なのです。死亡保険金は、遺産分割において他の相続財産とは別扱いとなっており、遺産分割協議とは関係なく受け取って使うことができます。 生命保険は、相続発生後の納税資金として非常に利用価値が高いのです。
貯蓄性の高い生命保険の場合には、満期を迎えた後、保険金を受け取りまで保険会社で据え置きしておけば、銀行に貯蓄しておくよりも高利率での資産運用が可能です。
相続税対策として比較的簡単に利用できる生命保険ですが、注意しなければならないこともあります。
これは絶対に間違ってはいけない注意点です。生命保険であれば、どのような契約内容であっても相続税対策になるというわけではないのです。
生命保険に課される税金は、保険料支払者(契約者)、被保険者、受取人が誰なのかによって、相続税、所得税と住民税、贈与税のどれかになります。
生命保険はいつでも誰でも入れるものではありません。年齢や健康状態などにより左右され、一般的には歳をとるほど入りにくくなっていきます。
通常、相続税対策を考える時期にはある程度の年齢に達している人が多いので、入りたい商品があってもスムーズにいかない場合があるということを頭に入れておきましょう。
「2-1.保険内容によって税金が異なる」の内容を、契約パターン別で具体的に解説します。
以下の各パターンは、夫婦と子供がいる家族で、夫が被相続人となる場合を仮定します。
「保険料の負担者=被保険者」であるため、相続税が課されます。一般的には、最も節税効果が高い契約内容になります。
上記「1-2.非課税枠」で解説した、「生命保険金の非課税枠」の適用があるのはこのパターンのみですので、よく覚えておきましょう。
ただしこの場合には、死亡保険金が非課税枠内であった場合でも、すべての相続人がすべての相続財産を知る権利がありますので、保険金受け取りの事実を知らせる義務があります。死亡保険金は、他の相続人に内緒では受け取れないのです。
「保険料の負担者=保険金の受取人」であるため、所得税と住民税が課されます。
また、保険金の受け取り方法によって所得の種類が変わり、一括で受け取る場合には一時所得、分割で受け取る場合には雑所得となります。
この場合の死亡保険金は相続財産ではありませんので、他の相続人に知られることなく保険金を受け取ることが可能です。
保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人の全てが異なる場合には、贈与税が課されます。
贈与税の税率は相続税に比べて高いので、一般的には不利なパターンといえます。
| 保険料支払者 (契約者) | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
| パターン① |  夫 夫 |  夫 夫 |   妻または子 妻または子 | 相続税 |
| パターン② |  妻 妻 |  夫 夫 |  妻 妻 | 所得税、住民税 |
| パターン③ |  妻 妻 |  夫 夫 |  子 子 | 贈与税 |
相続税対策としての生命保険の活用は、パターン①の相続税の場合が、生命保険の非課税枠の適用もあり最も大きな節税額となります。 特別な事情がある場合を除いては、このパターンで生命保険契約を結ぶようにしましょう。
最後に、おすすめの保険加入の仕方と、上記パターン②での節税方法を解説します。
生命保険には大きく分けて、定期保険、終身保険、養老保険がありますが、相続税対策として有効なのは、死亡時に必ず死亡保険金がもらえる終身保険です。
更にその中でも、支払っていく保険料を積み立てることが可能で、何らかの事情で途中解約した場合でも返戻金を受け取ることができる、貯蓄型がおすすめです。
経済的に余裕のある人は、保険料の一括払いをおすすめします。
将来的に支払う保険料をまとめて支払うため、一時的な資金負担が必要になりますが、結果として支払う保険料の合計額に対し、保険金の割合が高くなるため、相続税をより節税することができます。
一時払い終身保険は、昨今における日銀マイナス金利政策の影響を受け、各保険会社で縮小や販売を止める方向となっています。
そこで次の相続税対策として使える生命保険は、次の2つの保険が考えられます。
「生命保険金の非課税枠」を利用した節税ができるのは、パターン①の相続税が課される場合だけですが、上記のパターン②の所得税と住民税が課される場合でも、節税する方法があります。
事情によりパターン①の方法が選べなくても、まだ節税を諦めてはいけません。
| 保険料支払者 (契約者) | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
|---|---|---|---|---|
| パターン② |  妻 妻 |  夫 夫 |  妻 妻 | 所得税、住民税 |
パターン②の場合において、死亡保険金を一括で受け取った場合には一時所得として、所得税と住民税が課されます。
この一時所得は次の算式で計算されます。
※他の一時所得がない場合の想定です。
よって、死亡保険金額から支払ってきた保険料と50万円が差し引かれ、更にそれの半額が課税所得となるため、保険金として手に入れた現金額を考えると、それほど大きな税負担でないことが分かります。
ただし、これは保険契約者の妻が、保険金を支払うための十分な財産を持っている場合に利用ができます。また、被相続人の相続財産を減らす対策にはなっていませんのでご注意ください。
これは贈与税の基礎控除110万円を利用して、上記「4-4-1.一時所得の活用」の保険契約者の妻に保険料の十分な支払い能力がない場合をカバーすることができる方法です。
被保険者の夫から妻に対して、年間110万円以内で保険料分の現金を毎年贈与することで、贈与税がかかることなく、夫の財産を妻へ移していくことが可能となります。
生命保険による相続税対策のポイントは、契約によって課される税金が異なる点です。一般的には相続税が課されるパターンが、最も節税効果がありますが、場合によっては所得税や贈与税のパターンが良い場合もあります。
また、生命保険会社や取扱商品は数多くあり、専門知識のない人がベストな方法を判断するのは難しい場合が多いでしょう。
税理士などの専門家に相談すれば、相続財産の金額、相続人の構成、加入する保険の種類、収入や支出状況などに応じてアドバイスが貰えます。節税できる金額を考えれば、税理士費用など大した問題ではなかったということも多くあります。