相続税に強い税理士ってどんな税理士?
税理士にもそれぞれ得意分野があり、全ての税理士が相続税申告を得意としているわけではありません。「相続税に強い税理士」…[続きを読む]
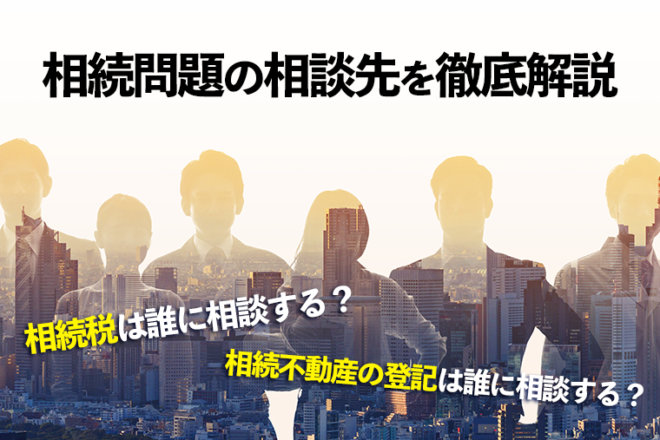
相続に関連した仕事をする主な国家資格には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士の4つがあります。相続は一生に何度もあるものではありませんので、いざ相続が発生すると相談先に迷ってしまうことがあるかもしれません。
そこで、それぞれの士業の違いと相続問題の相談先について整理してみます。
目次
税務相談、税務書類の作成、税務代理は税理士のみが担当することができます。
よって、相続税対策や相続税申告など、相続でも税金に関することは、税理士に相談します。
税理士は、相続税の申告書を相続人の代わりに作成・提出し、必要であれば税務署と折衝します。税金の相談と申告代理は税理士だけが許可された業務(※)ですので、相続税を申告するとき、被相続人の準確定申告をするときには、税理士に依頼することになります。
※ ただし、弁護士は、国税局長へ通知するか税理士登録をすれば税理士業務を行うことができます。
また、生前、相続税について、具体的に税金の計算を行い綿密な予測を立て対策したいときは、税理士に相談します。
特に、相続税対策では、贈与税や不動産等を売却した際に発生する譲渡所得税などの税金とも合わせてトータルで対策を考える必要があります。自分である程度できそうな場合でも、一度は税理士に相談してアドバイスを求めると良いでしょう。
事業承継では、自社株の評価が重要ポイントで、こちらも税理士の対応事項になります。
ただし、相続税について相談する税理士選びは慎重にしなければなりません。相続税について詳しい税理士とそうでない税理士は大きく違うのです。相続税対策や申告をどのような税理士に相談すればいいのかについては、以下の関連記事を是非ご一読ください。
遺言書作成について、税理士も対応可能ですが、遺言書作成のみで積極的に案件を受けることはあまりなく、どちらかというと、相続税対策とセットになります。最近では、「信託」に力を入れている税理士事務所もあります。
遺産分割協議書作成について、相続税申告を行うためであれば、税理士も対応可能です。
ただし、遺産分割協議の代理をしたり、遺産分割協議書作成だけを請け負うことはできません。
相続で次のようなことにお悩みであれば、相談先は税理士です。
相続税申告の期限は相続開始後10ヶ月以内ですので、できる限り早めに依頼するようにしましょう。
相続について争いがある場合、代理人として調停・裁判に参加できるのは弁護士だけです。
遺産相続において、親族間で争いごとがおきてしまい遺産分割協議がまとまらないような場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士の一番の特徴は、依頼人の「代理人」となって遺産分割協議を進め、場合によっては、裁判所での調停や裁判の手続きを行うことができることです。
弁護士に依頼すれば、依頼人に代わって弁護士がすべて窓口となって対応してくれるため、面倒な親族間の話し合いに参加する必要もなくなります。交渉自体を任せることができるため、相続協議の煩わしさからは一切開放されることができます。
また、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停に発展した場合でも、そのまま代理人として対応ができます。
これに対し、他の専門家は、依頼人の代わりに他の相続人と直接交渉することができません。
また、弁護士には、遺産分割協議以外にも、相続放棄、遺留分侵害額請求などの法的行為や、遺言書の作成、成年後見人の依頼もできます。
相続登記についても弁護士は対応可能ですが、非常に専門性が高いため、連携する司法書士に依頼することが一般的です。
弁護士は、何でもできるオールマイティ的な存在ですが、依頼者側からすると、他の専門家より報酬が高いことが、問題になることがあります。
家族間でもめてしまったとしても、相続財産の金額が少なければ、弁護士報酬を支払ってまで財産を獲得する意味がなくなりますから、そのような場合には、後述する司法書士や行政書士に依頼したほうが良いこともあります。
相続で次のようなことにお悩みであれば、相談先は弁護士です。
不動産を相続した場合に必要となる「相続登記」は、司法書士が相談先となります。
相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。
この相続登記を依頼人に代わって申請できるのは、司法書士と弁護士だけです。
ただ、登記についてはその道の高度な専門知識と実務経験が必要であり、弁護士が担当することはほとんどなく、基本的には、相続登記は司法書士の独壇場といえます。
各種の相続手続き(金融機関での手続きなど)を代理で行ってくれる事務所もあります。
その他、司法書士は、成年後見人の申し立てや、遺言書、遺産分割協議書の作成や相続放棄、遺産分割調停に必要な裁判書類の作成などを行うことができ、弁護士よりも報酬が低く、依頼しやすいといった特徴があります。
ただし、一般的な相続問題では、相続人を代理することはできません。
相続で次のようなことにお悩みであれば、相談先は司法書士です。
行政書士は、相続に関する書類の作成や収集を行います。
行政書士は「書類作成のエキスパート」であり、遺産相続においては、遺産分割協議書や遺言書を作成することができます。
相続でもめていない、相続税申告も発生しない、相続登記もないという場合には、遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼すると良いでしょう。
相続が発生すると被相続人の口座が凍結されてしまい、解除するには、遺産分割協議書が必要になりますが、行政書士であれば、比較的安価な報酬で対応してもらえます。
弁護士と違い、行政書士は、法律相談に乗ることはできません。ただし、遺産分割協議書を作成するための相談には乗ることができるため、形式的に間違った遺産分割協議書を作成してしまうのを防ぐことができます。
相続で次のようなことにお悩みであれば、相談先は行政書士です。
上記4資格者が可能な相続関連業務について比較してみました。
| 税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
|---|---|---|---|---|
| 相続税対策 (生前) | ○ | × | × | × |
| 遺言書作成 (生前) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続人調査 相続財産調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金融機関での 手続き | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続放棄 | × | ○ | △ (制限あり) | × |
| 準確定申告 | ○ | × | × | × |
| 遺産分割 協議書作成 | △ (申告を伴う 場合のみ) | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割調停 | × | ○ | × | × |
| 相続登記 | × | ○ | ○ | × |
| 相続税申告 | ○ | × | × | × |
○:可能、△:部分的に可能、×:不可能
それぞれの専門家ごとに対応できる範囲が異なりますが、多くの士業事務所は、他士業と連携していますので、どこか一つの事務所に依頼すれば、その他の内容もワンストップで対応してもらえます。
たとえば、相続税申告で税理士に依頼したけれど相続登記も必要で司法書士にも依頼したいというケースでは、別途、司法書士を探さなくても、税理士から連携する司法書士を紹介してもらえることが多いでしょう。相続不動産に関する内容もあらかじめ税理士から司法書士へ話をしておいてもらえます。
つまり、窓口がどこになるかの違いだけで、最終的に受けられるサービス内容に大きな違いはありません。
争いもなく、相続税申告も登記も予定しておらず、相続について不安だから相談したいという場合、あるいは、相続に関する一般的な知識を知りたいという場合には、上記の国家資格者以外にも、相続に関連する民間資格者や、FP、不動産会社、銀行、保険会社に相談するという手もあります。
相続全般について相談したいのであれば、FP(ファイナンシャル・プランナー)や相続アドバイザー、相続診断士など、不動産や銀行口座、保険など特定の分野について相談したいのであればそれぞれの民間企業が相談先として存在します。
最近では、初回の相談を無料で行うといった士業の事務所も増えています。
是非、電話やメールで問い合わせて、上手に利用して、相続問題を解決しましょう。