子供・孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税に【2023年版】
祖父母や父母から子供や孫へ、教育のための資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。制…[続きを読む]
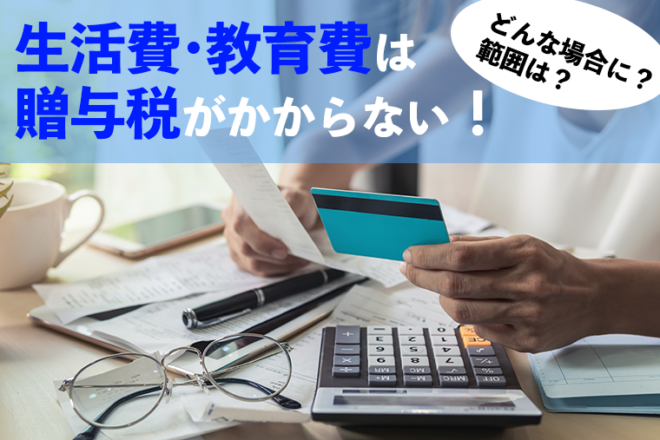
通常、年間で110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた場合は、「贈与税」が課されます。しかし財産の性質や、贈与の目的によっては、贈与税がかからないものがあります。生活費や教育費など社会通念上妥当と認められれば、贈与税の課税対象にはなりません。
このことを認識していれば、基礎控除額や、各種の特例制度にこだわらずとも、子供や孫にお金を贈与することができます。
そこで、贈与税がかからない場合についてご説明します。
目次
最初に、贈与税がかからない贈与の中で、一番身近な扶養義務者からの贈与について説明します。
相続税法21条の3に、贈与税の非課税財産として、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」という規定があります。
この内容を具体的1つ1つに説明しましょう。
ここで言う「扶養義務者相互間」とは、受贈者(贈与を受ける人)と受贈者を扶養する立場にある人のことです。扶養義務者の範囲は民法877条によって次のように規定されています。
したがって、贈与者と受贈者との関係が、例えば夫婦間、親子間、兄弟間などであれば「扶養義務者の範囲内」として見られます。つまり、金品等の贈与をしても贈与税の対象外として扱われます。
相続税法21条の3で言う「生活費」とは、「その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)」をいいます(相続税法基本通達21の3-3)。治療費、養育費などを含みます。
【参考】第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁
「教育費」は、「被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等」を言い(相続税法基本通達21の3-4)、義務教育にかかる費用に限りません。言い換えれば、扶養相手に教育を受けさせるための学費等ということになります。
【参考】第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁
では、「通常必要と認められるもの」とはどういったものなのでしょうか?
相続税法基本通達21の3-6に「通常必要と認められるものとは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」とあります。
【参考】第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁
「生活費」や教育費」で、「社会通念上適当と認められる範囲」と言われても、まだ、わかりずらいかもしれません。そこで具体例を挙げて説明しましょう。
生活費として認められる具体例には、以下のようなものがあります。
子供の生活費として仕送りをしたり、子供が一人暮らしをしているアパートの賃貸料を贈っても、贈与税の課税対象にはなりません。
例えば、子供に毎月10万円以上、仕送りをしている親御さんもいらっしゃると思いますが、年間にしたら120万円で基礎控除額の110万円をオーバーしていますが、それで贈与税を申告したという話は聞いたことがないでしょう。
子供の結婚は親としては大変嬉しいものであり、それなりの金額を子供にあげる親も多いと思います。
子供の結婚式や披露宴の費用を親が負担することについても、それがその地域の慣習や社会常識、招待客との関係などに照らして妥当であれば、贈与税が問題になることはありません。
派手好きな親族が多い家系で親の顔を立てるために豪華なホテルで結婚式をすれば費用もそれなりにかかるでしょう。実際、親から100万円ほど援助してもらったという話はたくさんありますし、中には親の意向で1,000万円出してもらった人もいるようです。
新婚生活は何かと物入りです。冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電、食器棚、キッチンテーブル、衣装ダンス、ベッドなどの家具、その他、日常生活を送るために必要なものを購入するのであれば、贈与税が問題になることはありません。
新婚生活に必要な物をひととおり揃えるだけで100万円くらいかかります。子供の結婚を機に、思い切って支援してあげるのも一つの手です。
次に、子供が出産する、つまり孫ができるのは嬉しいものですが、その出産費用を子供に贈与しても贈与税は非課税です。
具体的には、出産のための検査費用、入院費用、治療費用等があります。また、出産後の新生児の生活に必要なベビー用品等を購入することも含まれます。昨今では子育てもお金がかかる時代ですので、出産した子供の助けにもなるでしょう。
【参考サイト】扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 平成 25 年 12 月|国税庁
教育費用として認められる具体例には、次のものがあります。
教育費は義務教育に係る費用を基本とし、このために必要な教育必要全般が含まれます。該当するのは、以下のような費用です。
また、学習塾や受験費用等も教育の中に含まれます。
注意すべきは、生活費や教育費であっても、社会通念上適当と認められる範囲でなければ非課税とならないということです。
例えば、贈与者(親)と受贈者(子供)の収入等によっては贈与として認められないこともあります。もし、子供がベンチャー会社を経営していて数千万円の年収があり親よりも収入が多かったら、親が子供を扶養すべきとはいえないからです。
また、現金を使わずに貯金しておいたり、それを元手に株式投資をしたりすると贈与税が課される可能性があります。税務署は、やりとりした金額の大小よりも、あくまでも実体で判断しています。
生活費を1年分まとめて渡してしまうと、贈与となり贈与税がかかる可能性があります。必要な限度を超えてお金を渡すと、もらった側が生活以外にも自由に使いうるからです。
確実に贈与税がかからないようにするためには、生活費をその都度(たとえば毎月ごと)、渡すようにしましょう。
扶養義務者以外からの贈与でも、社会通念上妥当と認められる内容と金額であれば、以下のものに贈与税は課税されません。
入学祝い、結婚祝い、出産祝いなどで、同僚、上司、知人、友人などから金品を受け取ることがありますが、これらも社会常識的な範囲であれば非課税です。
宗教や慈善、学術などの公益を目的とする事業を行っている人が、その事業のために財産を受け取った場合には、贈与税がかかりません。
また、特定公益信託から、奨学金を目的として支給される金品も贈与税の対象外です。
【参考サイト】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁
精神や身体に障害を持つ人が、自治体等から給付金を受ける場合も対象外です。
【参考サイト】障害者と税|国税庁
そのほか、離婚時の慰謝料や養育費や財産分与も贈与税の対象外です。交通事故での損害賠償金も非課税です(相続税法基本通達9-8)。
ただし、その金額が過大である場合には贈与税がかかるケースがあります。
【参考サイト】No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁
贈与税は「個人から個人に」贈与された財産に対して課税される税金です。法人から個人へ、逆に個人から法人へ贈与を行っても贈与税の課税対象とはなりません。
【参考サイト】No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
ただし、「法人から個人へ」贈与された財産には、所得税を納める必要があります。たとえば、ある社員が会社から土地を無償でもらったとしたら、給与所得として所得税が発生します。
また、「個人から法人へ」贈与された財産には、贈与税ではなく、法人税が発生します。ただし、例外として代表者または管理者が定められている人格のない社団または財団等が個人とみなされて(みなし個人)、贈与税を課税される場合があります。
参考までに、贈与者(贈る側)、受贈者(受ける側)がそれぞれ個人、法人の場合に課税される税金について整理しておきます。
| 受贈者 (受ける側) | |||
|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | ||
| 贈与者 (贈る側) | 個人 | 贈与税 | 法人税 |
| 法人 | 所得税 | 法人税 | |
贈与税がかからない場合について解説してきましたが、贈与税が非課税となるケースは意外と多いものです。必要な時に必要な金額だけ子供や孫に贈与することで、税金を気にすることなく、贈与することができます。
一方で、お金を受け取った子供や孫も、適宜必要なお金を援助してくれる親や祖父母に対して感謝を抱いたり、必要なところに大切にお金を使ってくれるでしょう。
ここでご説明した以外にも、教育資金、結婚・出産資金の贈与については、それぞれ一定金額まで非課税となる特例制度があります。
また、要件を満たせば、リフォームやマンションなど不動産の住宅取得資金の贈与を、最高3,000万円を限度として非課税で受けることが可能です。
ご不明な点等は、是非、相続に強い税理士にご相談ください。