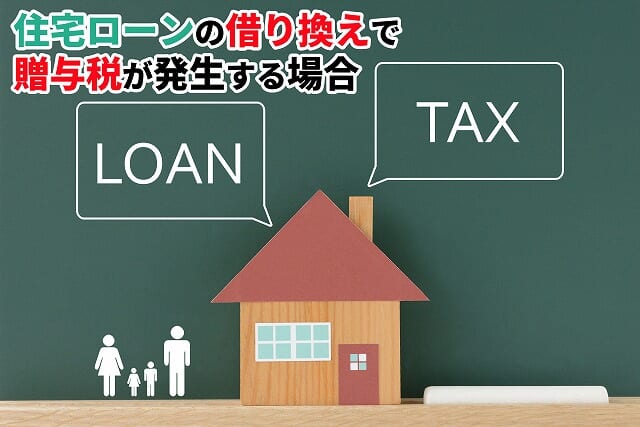本当に今が借り時なのか?アパートローンの基礎知識と現状

このところ、相続対策でローンを組んでアパート経営を始める人が増えています。親の土地を相続し、アパート経営をすることになった人もいるでしょう。アパートローンに関する基礎知識や、アパートローンの現状について解説します。
目次
1.アパートローンとは
アパートローン(アパート融資)とは、金融機関が、主に土地を所有する個人に対して行う、アパートの建設資金の融資のことです。アパートローンの基本的な仕組みを見てみましょう。
1-1.アパートローンの基本的な仕組み
アパートローンの借り手は、借りた資金をアパートなど賃貸用不動産の購入や新築、増築、改築などに充てます。家賃収入でローンを返済するのが一般的です。借り手は、
- 土地を更地で持っているよりも、アパートを建てたほうが相続税を減らせる
- 家賃収入のほうがローンよりも多いので、余裕で返済できる
などの理由でアパート経営を決め、アパートローンを借りるケースが多いです。
1-2.住宅ローンとの違い
アパートローンは住宅ローンとは全く異なります。住宅ローンは、自分が住む住宅に対してのローンであるのに対し、アパートローンは、他人が住む住宅に対してのローンであり、事業目的(営利目的)といえます。
そのためアパートローンでは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることはできません。また、住宅ローンを組んでアパート経営をすることもできません。この場合、もし金融機関に発覚したら、何らかのペナルティを受けることになります。
1-3.借入条件
次に、アパートローンの借入条件を、金融機関各社の商品概要から確認しましょう。

1-3-1.借入可能額
借入可能額は、金融機関によって異なりますが、下限は100万円のところが多いです。
上限は1億円、3億円、5億円などさまざまで、「担保価格の範囲内」というところもあります。
1-3-2.借入期間
借入期間は、1年以上35年以内が多いですが、なかには25年以内、30年以内というところもあります。
1-3-3.金利の仕組み(固定金利、変動金利)
金利については、変動金利(連動金利方式)、固定金利(全期間固定、当初固定金利)から選択できる場合が多いです。
1-3-4.返済方法(元利均等返済、元金均等返済)
返済方法は、元利均等返済のところがほとんどです。
1-4.借入先金融機関
次に、借入先金融機関について、業態別に見てみましょう。
1-4-1.都市銀行
メガバンク3行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行)のなかでは、三菱東京UFJ銀行は比較的消極的と思われます。
1-4-2.地方銀行
地方銀行は基本的にどこも、アパートローンを積極的に取り扱っています。地方の多くは、企業向けの融資が伸び悩んでおり、地方銀行は収益源をアパートローンに求める傾向があるからです。この傾向は、2016年2月からの日本銀行によるマイナス金利政策の導入以降、顕著になりました。
1-4-3.信用金庫
信用金庫も、基本的にアパートローンを積極的に取り扱っています。なお信用金庫の場合は、借入対象者の要件として「当金庫の営業地区内に住所または居所、事務所を有する方」、「当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方」という制限があることが多いので注意しましょう。
1-4-4.その他金融機関
上記以外にも信託銀行やノンバンク系金融機関などが取り扱っています。
1-5.審査のポイント
アパートローンの審査項目は金融機関によって異なりますが、主に次のような点がチェックされます。
- 保有する土地(そもそも土地を保有していないと、融資を受けることができない場合がほとんどです)
- 職業および安定した収入の有無
- 他のローンの状況
ただしここ数年、「アパートローンの審査は全般に甘くなっている」という声が多く聞かれます。背景には、前述のマイナス金利政策の影響で、貸出競争が激化していることがあると思われます。

1-6.金利水準
アパートローンの金利は、一般的に住宅ローンの金利よりかなり高いです。そして、金融機関のホームページや商品概要書を見ても、「詳細は店頭にてお問い合わせください」とされていることが多く、実態がわかりにくくなっています。
ホームページに店頭表示金利のみ掲載されているところもありますが、住宅ローンの金利のように、ディスカウント後の金利が掲載されているところは少ないです。
しかしながら、前述のマイナス金利政策の導入による市場金利の低下を受け、アパートローンの金利も全般に低下していることは間違いありません。
一例を示しますと、あるノンバンク系金融機関の2017年6月12日現在のアパートローンの金利は、
- 変動金利型:年2.35%(店頭表示金利からの割引幅▲1.325%)
- 3年固定特約型:年1.975%(固定金利期間特約付変動金利型・店頭表示金利からの割引幅▲1.325%)
- 5年固定特約型:年2.175%(固定金利期間特約付変動金利型・店頭表示金利からの割引幅▲1.325%)
となっています。
1-7.その他
アパートローンでは、融資にあたり、当該金融機関が融資対象となる土地および建物に、第一順位の根抵当権を設定登記します。また建物については、原則として火災保険に加入し、その保険金請求権等に質権を設定します。
保証人については、1名ないし2名を連帯保証人とする場合が多いですが、なかには保証人不要としているところもあります。
1-8.借り換えは可能?
アパートローンの借り換えは基本的に可能です。むしろ、各金融機関とも借り換えを積極的に受け入れています。商品概要書の資金使途のところでも、「現在他金融機関から借り入れ中のアパートローンの借り換え資金」と明確にうたっているところも散見されます。
1-9.返済シミュレーション
では、どれくらいのアパートローンを借りたら、毎月いくら返済することになるのか、実際の例で見てみましょう。
新しくアパート経営を始める場合、小規模な土地であれば、「2階建て・4部屋・建設費4,000万円前後」という例がよく見られます。この前提で、前述のあるノンバンク系金融機関で「借入金額:4,000万円、返済期間:20年、変動金利:2.35%」で借りた場合、
| 毎月の返済額 | 209,050円(年間返済額:2,508,600円) |
|---|---|
| 総返済額 | 50,172,000円(利息合計:10,172,000円) |
となります。(変動金利ですが、便宜上、返済期間中は金利が変わらないものとして試算しています)
この例では、アパートは4室ですので、例えば毎月の家賃が53,000円以上あれば、
53,000円×4=212,000円>209,050円となり、
家賃がローンを上回ることになります。
仮に家賃が7万円であれば28万円の家賃収入となり、計算上は毎月7万円強の剰余が発生することになります。ただしもちろん、実際にはその他の経費や、空室率も勘案する必要があります。
2.アパートローンの現状
ここまで、アパートローンの概要や基本的な仕組みを見てきましたが、これからアパート経営を始め、アパートローンを組む人は、アパートローンの現状を確認しておいたほうがよいでしょう。
2-1.アパートローン急増の背景
アパートローンは、ここ数年急速に新規貸し出しおよび残高が急増しました。背景にあるのが、次の三点です。

2-1-1.相続税基礎控除引き上げ(2015年1月~)
まず、2015年1月からの相続税の基礎控除引き上げ(および一部税率引き上げ)が挙げられます。相続税の課税対象者が急に増えたため、相続税対策として、多くの人がアパート経営を始めました。
2014年の半ば以降、書店では相続関連の書籍が増え、相続コーナーが拡大されたことを覚えている人も多いでしょう。その少し前からのいわゆる「終活」ブームとも相まって、アパート経営が注目され、アパートローンが急速に増加しました。
2-1-2.日銀によるマイナス金利政策(2016年2月~)と貸出競争の激化
さらに、前述のマイナス金利政策の導入による貸出競争の激化もアパートローンの急増に拍車をかけました。また貸出金利が大きく低下したことで、アパートローン自体も利用しやすくなりました。
2-1-3.サブリース
もう一つ、サブリースの広がりも見逃せません。サブリースとは、賃貸住宅メーカーが、「アパート建設のみならず、一括借り上げし入居者募集も行う。家賃の最低保証もする」というものです。
借り手側から見ると、手間もかからず家賃保証もあるので魅力的に見えます。このサブリースは借り手の心をとらえ、契約が急増しました。そのため、大手賃貸住宅メーカー各社の2017年3月期決算は総じて好調でした。最高益更新の会社も見られます。
2-2.過熱するアパートローン
しかし、現在のアパートローンの状況は過熱気味です。例えば、2016年6月以降の1年間で、大手新聞5紙では10回以上、アパートローンの過熱ぶりを取り上げています。2016年8月には、その過熱ぶりを社説で警告した新聞もあるくらいです。アパートローンの現状を、データをもとにいろいろな角度から見てみましょう。
2-2-1.不動産業向け融資(個人による貸家業向け)の現状
日本銀行が発表している「貸出先別貸出金」によると、国内銀行の業種別期末貸出残高のうち、「個人による貸家業向け」は、33.49兆円(2015年3月末)→34.45兆円(2016年3月末)→35.86兆円(2017年3月末)と、このところ約1兆円ペースで増加しています。全業種で見ても、特筆すべき高い伸びといえます。
2-2-2.新設住宅着工戸数の現状
国土交通省が発表している「新設住宅着工戸数」によると、借家系の着工戸数は、
36.6万戸(2014年度)→39.0万戸(2015年度)→43.3万戸(2016年度)と、融資同様高い伸びを示しており、アパート建設が盛んに行われていることが伺えます。

2-2-3.空き家の現状
総務省統計局が5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」の平成25年度調査によると、空き家は820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と過去最高になっています。高齢化や少子化、都市一極集中、地方の過疎化を考えると、空き家の増加傾向は今後も続くものと思われます。
需要と供給で見た場合、空き家が増え続けているのに、アパートの建設ラッシュが続いているのは、普通に考えたらおかしな現象といえるでしょう。
【関連】空き家の3大リスクと相続に向けた対策:売る、貸す、維持管理
2-3.警戒強める日銀、金融庁
このアパートローンの過熱ぶりに、日本銀行や金融庁は昨年から警戒を強めています。
日本銀行は、2017年4月19日に公表した金融システムリポート「地域銀行の不動産向け貸し出しについて」で、「貸家市場における需給緩和を懸念する声も一部で聞かれ始めている」と指摘し、地域金融機関へ、「入口審査の厳格化を通じた与信管理の向上の必要性」を訴えています。
金融庁も、昨年来アパートローンの監視を強めています。2017年に入り、特にアパートローンの伸びが顕著な地方銀行に対し、契約内容の詳細を提出させるなど、アパートローンの実態調査に着手しています。
内閣府も、2017年1月のレポート「経済財政分析ディスカッション・ペーパー(貸家建設と潜在需要)」でモデルを用いた分析を行い、「2016年以降は、貸家着工が足下の増加ペースが続けば、潜在需要を上回り、供給過剰になり得る」と明言しています。
2-4.今はアパートローンバブルなのか?
 アパートローンは、土地が担保になるため、金融機関にとっては比較的安心で利ザヤも稼げる商品です。しかし昨年来、「アパートローンバブル」を懸念する声は少なくありません。家賃保証をめぐるトラブルも顕在化しており、客観的に見ても今は「バブルの手前」まで来ていることは間違いないでしょう。
アパートローンは、土地が担保になるため、金融機関にとっては比較的安心で利ザヤも稼げる商品です。しかし昨年来、「アパートローンバブル」を懸念する声は少なくありません。家賃保証をめぐるトラブルも顕在化しており、客観的に見ても今は「バブルの手前」まで来ていることは間違いないでしょう。
今後もし、需要を無視したアパート建設ラッシュが続き、アパートローンが伸び続けるようであれば、日本でも、サブプライムローン問題に端を発するリーマン・ショックのような事態が生じても不思議ではないといえます。
2-5.まとめ
相続税対策のためのアパート建設は、メリット、デメリットおよびリスクをしっかり確認し、身の丈を踏まえてアパートローンを借りれば何ら問題はありません。ただし今は一種のブームになっていますので、周囲に流されて始めることだけは避けましょう。
アパートローンの仕組みや基礎知識をしっかり押さえ、現状も理解したうえで、もし必要になる場合は、賢くアパートローンを利用しましょう。