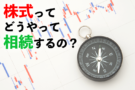損害保険の相続手続きと相続税

損害保険は生命保険と異なり、相続の場面で登場することは比較的少ないといえます。生命保険に比べ、保険期間が短い商品が多いためです。
しかし、損害保険も、個人のリスクマネジメントにおいては、生命保険同様、重要な役割を果たしており、死亡時に支払われる保険金が相続税の対象となることもあります。
損害保険の相続手続きと相続税について解説します。
目次
1.損害保険の相続手続き方法
1-1.手続き先、必要書類
損害保険の契約者が死亡した場合は、まず担当している代理店(または損害保険会社の営業店)に連絡しましょう。
相続に必要な書類のセットを郵送あるいは届けてくれます。
ただし、代理店名や担当者名が分からない場合は、損害保険会社のコールセンターに連絡してください。担当代理店や営業店につないでくれます。
必要書類は、被相続人が加入していた保険により、また損害保険会社により異なりますが、被相続人の契約を名義変更して継続する場合は、主に次の書類が必要になります。
- 相続に関する書類・・・被相続人の死亡および法定相続人が確認できる戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割
協議書、遺言書等 - 損害保険会社が指定する書類・・・各種申請書や保険金請求書など
1-2.名義変更、解約
損害保険の契約者が死亡し、相続人が契約を引き継ぐ場合は、名義変更をする必要があります。名義変更の手続きは、保険の種類により方法や必要書類が異なります。
契約を引き継がずに解約する場合は、名義変更に比べて事務負荷は小さくなります。損害保険会社所定の書類を提出すれば完了します。
2.損害保険と相続税
次に、損害保険を相続して相続税が課税されるケースを考えてみましょう。
2-1.積立式で解約返戻金のある保険(積立火災など)
損害保険には、解約返戻金があるものもあります。代表例が積立式の火災保険(積立火災)でしょう。市場金利が現在よりも高い頃は、多くの損害保険会社が活発に販売していました。
積立式火災保険を相続した場合、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額(いわゆる積立部分)となります。
例えば、JA共済の「建物更生共済」は、掛け捨てではなく、保障期間満了時に満期共済金を受け取ることができるタイプの商品です。国税庁のホームページには、この建物更生共済の相続時の課税関係について、以下のように照会とそれに対する回答があります。
<照会要旨>
甲は、乙所有の建物の共済を目的とする建物更生共済に加入し、掛金を負担していました。甲または乙について相続が開始した場合、建物更生共済に関する相続税の課税関係はどのようになりますか。
(契約関係)
共済契約者(掛金負担者):甲(長男)
被共済者(建物所有者):乙(父)
満期共済金受取人:甲
<回答要旨(抜粋)>
共済契約者甲について相続が開始した場合には、建物更生共済契約の約款によれば、共済契約者の相続人に契約が承継されることになっていることから、建物更生共済契約に関する権利が甲の本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。(以下、省略)

2-2.掛け捨て型だが、一時払いで解約返戻金のある保険
掛け捨てタイプですが、保険料を一時払いで払う保険には、解約返戻金があるものもあります。
金融類似商品とよばれるタイプで、生命保険に多く見られますが、損害保険にも一部あります。
この場合も、相続発生時には上記の積立式火災保険同様、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額となります。
3.損害保険の保険金の課税関係
損害保険の保険金を受け取る場合、保険料の負担者や支払原因により課税関係が異なってきます。ケースごとに、根拠法令とともに見てみましょう。
3-1.傷害保険で支払われる死亡保険金、非課税枠について
傷害保険で支払われる死亡保険金は、以下のように保険料負担者により課税関係が変わります。
3-1-1.被保険者が保険料負担者の場合
この場合は、保険金受取人が被保険者の相続人である場合は相続により、保険金受取人が被保険者の相続人以外の場合は遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます(所得税法第3条第1項第1号、相続税基本通達5-5-(1))。
3-1-2.保険金受取人が保険料負担者の場合
この場合は、所得税法の一時所得として取り扱われることになり、他の一時所得と合算して所得税が課税されることになります(所得税法第34条)。
3-1-3.第三者が保険料負担者の場合
この場合は、保険金受取人が第三者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されます(相続税法第5条第1項、相続税施行令第1条の5、相続税基本通達5-5-(2))。
【関連】相続対策での生命保険の活用法
3-1-4.非課税となる傷害保険の保険金
傷害保険では、本人または家族の傷害により受け取った後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金などは、所得税法上、非課税となります。
3-2.その他の保険で支払われる死亡保険金
今度は、自動車保険の死亡保険金について見てみましょう。
自動車保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険のうち被保険者自身の過失部分)の死亡保険金は、傷害保険同様、以下のように保険料負担者により課税関係が変わります。
3-2-1.被保険者が保険料負担者の場合
この場合は、保険金受取人が被保険者の相続人である場合は相続により、保険金受取人が被保険者の相続人以外の場合は遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税が課税されます(所得税法第3条第1項第1号、相続税基本通達5-5-(1))。
3-2-2.保険金受取人が保険料負担者の場合
この場合は、所得税法の一時所得として取り扱われることになり、他の一時所得と合算して所得税が課税されることになります(所得税法第34条)。
3-2-3.第三者が保険料負担者の場合
この場合は、保険金受取人が第三者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されます(相続税法第5条第1項、相続税施行令第1条の5、相続税基本通達5-5-(2))。
つまり、傷害保険の死亡保険金とまったく同じ扱いになります。それぞれの場合の根拠法令も同じです。

3-3.交通事故などの損害賠償金
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたとき、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の課税対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定があるため、原則として税金はかかりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合は、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります(相続税法第2条、所得税法第9条、所得税法施行令第30条、相続税タックスアンサーNo.4111)。
3-4.その他非課税となる損害保険金
ここでは、所得税法上非課税となる損害保険金(事故により支払われるもの)についてまとめます(所得税法第9条第1項第16号、相続税基本通達3-10、1999年10月18日付国税庁法令解釈通達「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について」)。
- 対人賠償保険:対人事故により支払われる保険金
- 対物賠償保険:対物事故により支払われる保険金
- 人身傷害保険:損害賠償的要素の保険金(被保険者の死亡・後遺障害・傷害に対する保険金のうち、加害者の過失による部分)、傷害保険的要素の保険金(被保険者の過失による部分として支払われる後遺障害保険金・医療保険金)
- 搭乗者傷害保険:被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
- 無保険者傷害保険:無保険車による事故により被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け取る保険金
- 自損事故保険:被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
- 車両保険:車両事故により被保険者に支払われる保険金
- 火災保険:火災・爆発などの事故により支払われた保険金
3-5.災害による損害
災害により住宅や家財に損害を受けた場合は、所得税の雑損控除(所得控除)または災害減免法(税額控除)の適用があることを覚えておきましょう。
この2つは重複適用できないため、どちらかを選択することになります。
4.まとめ
損害保険の相続手続きは決して難しくありません。また、生命保険と異なり、相続税の課税対象となるケースも限られています。ただし、損害保険は付保対象が広いため、それぞれの保険の種類や契約内容を把握し、理解するのはなかなか大変です。家族や親族が加入している損害保険の内容を予め確認しておき、万一相続が発生した場合でも困らないようにしたいものですね。