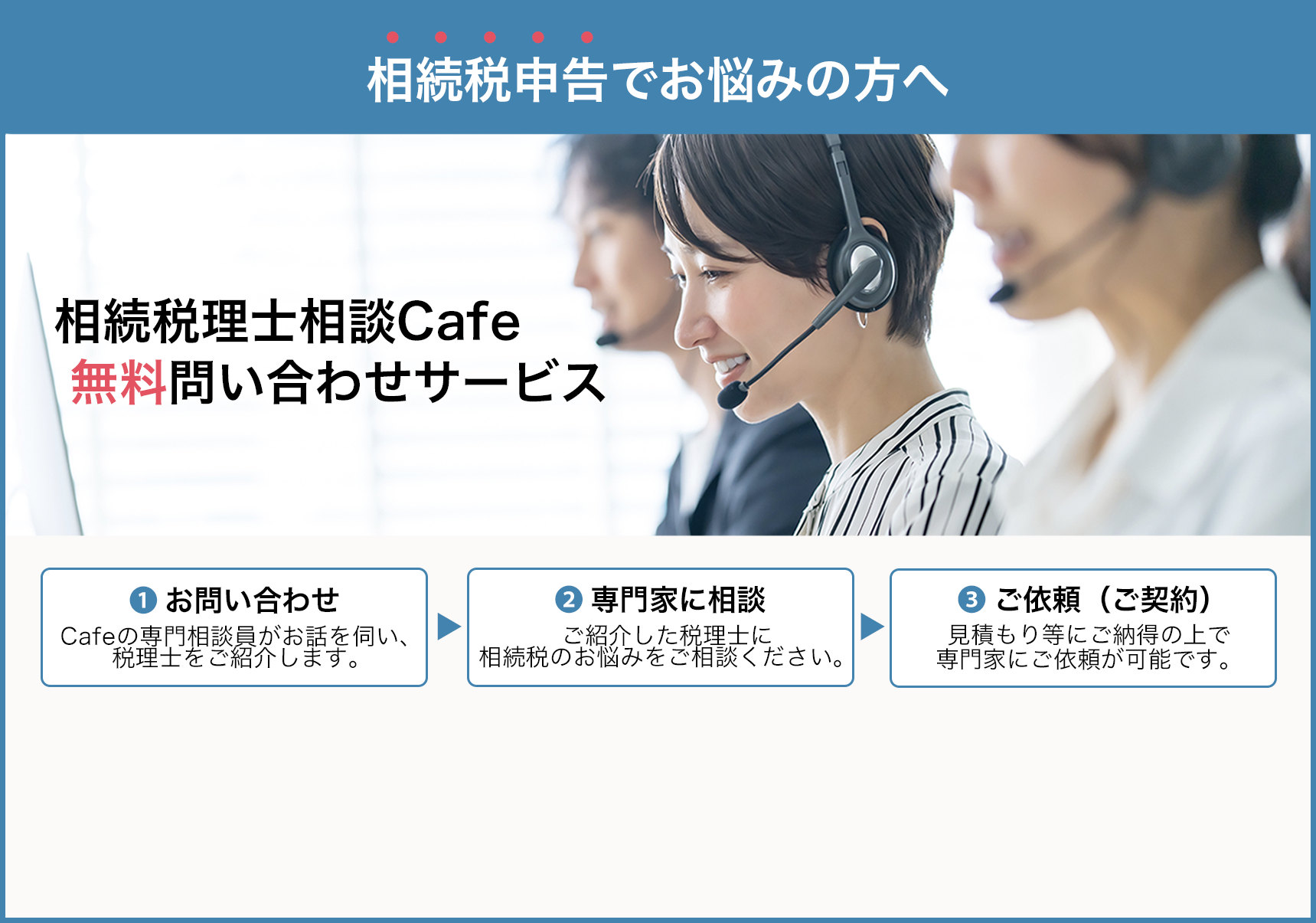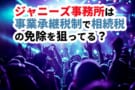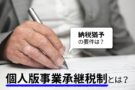事業承継補助金を賢く利用しよう

日本の中小企業の後継者不足は深刻であり、残していくべき価値ある事業も後継ぎがいないために、泣く泣く廃業している事業者も数多くいます。そのような状況を打開するために中小企業庁は、「事業承継補助金」を設けています。
以下では、事業承継補助金の概要、どのような企業が対象となるのか、どのように使えばよいかなど徹底解説します。事業承継を検討中の方必見です。
目次
1.事業承継補助金とは
1-1.概要と目的
事業承継補助金とは、中小企業や個人事業者の事業承継にかかる国の支援施策のことで、一定要件に該当する場合には、事業承継に必要な経費に対して補助金が交付される制度です。
2018年も継続して公募されることが決定していますが、2019年、2020年と今後も毎年公募されるかは分かりません。
この事業承継補助金が設けられた目的は、名称通り、中小企業の事業承継を資金面からサポートするためです。
日本には膨大な数の中小企業がありますが、その多くが後継者がいないという理由で、事業継続が困難な状況にあります。初代社長が率いる中堅企業においてはその7割が後継者不足であるというデータもあるのです。
日本の経済を支えている中小企業を存続させて、更に発展させていくために事業承継補助金は設けられています。
1-2.補助される金額
補助対象とされる経費(※)の2/3以内で、100~200万円が補助金として交付されます。
事業所の廃止や集約なども伴う場合には、更に300万円がプラスされ、最大上限額は500万円となります。
※事業承継補助金の補助対象となる経費は次の通りです。
| 区分 | 例 | |
|---|---|---|
| 人件費 | 人件費 | 新たな取り組みに従事する従業員の給与 |
| 事業費 | 申請書類作成費用 | 司法書士や行政書士の申請書類作成依頼費用 |
| 店舗等借入費 | 事務所、駐車場などの賃借料 | |
| 設備費 | 店舗や事務所開設のための工事費用 | |
| 原材料費 | 試供品制作の原材料費 | |
| 知的財産等関連経費 | 国内や外国の特許等取得費 | |
| 謝金 | 専門家に支払う謝金 | |
| 旅費 | PRのための交通費や宿泊料 | |
| マーケティング調査費 | 市場調査を行うための郵便代 | |
| 広報費 | パンフレットの印刷代 | |
| 会場借料費 | PR活動に使用するなど一時的な会場使用料 | |
| 外注費 | 業務の一部を第三者に外注する費用 | |
| 委託費 | 委託費 | 業務の一部を第三者に委任する費用 |
| 廃業費 | 廃業登記費 | 司法書士や行政書士に支払う登記手数料 |
| 在庫処分費 | 商品在庫を処分するための費用 | |
| 解体費及び処分費 | 既存事務所の解体費用 | |
| 原状回復費 | 借りていた事務所を返却する際の原状回復にかかる費用 | |
1-3.適用対象となる企業・事業者
事業承継補助金の交付対象となるのは、次の3つの要件全てを満たす者です。
- 事業承継が行われること
2018年12月31日までに事業承継(代表者の交代)が完了していなければなりません。 - 地域に貢献する中小企業であること
事業取引や雇用などによって地域経済に貢献している者でなければなりません。 - 新たな分野への取り組みを行っていること
新商品開発などの経営革新や、事務所の集約や廃止などの事業転換などの新しい取り組みを行わなければなりません。
2.補助金を貰うまでの流れ
2-1.流れ
| ① | 事業承継補助金についての知識を付ける | ネット検索、事業承継補助金事務局や認定支援機関(※)へ直接確認するなどして、ひと通りの知識を付けましょう。 2018年5月9日(月)から各地で開催される公募説明会に参加するのも方法の1つです。 |
|---|---|---|
| ② | 申請書類を入手する | 認定支援機関(※)へ事前相談を行い、地域貢献や経営革新などについての確認書を作成してもらう必要があります。 |
| ③ | 公募期間内に申請する | 確認書とその他必要書類を補助金事務局に提出します。 2018年の公募期間は、4/27(金)~6/8(金)です。 |
| ④ | 年末までに事業承継を完了させる | 申請時点で事業承継が終わっていない場合には、年末までに必ず完了しましょう。 |
| ⑤ | 翌年に採択結果が通知される | 事務局と地域審査会で審査が行われ、事務局から採択通知が送付されます。 ホームページで確認することも可能です。 |
※認定支援機関とは、税理士事務所、公認会計士事務所、弁護士事務所など、中小企業の経営相談先として国が認定している支援機関のことをいいます。
お住まいの地域の認定支援機関については、中小企業庁のホームページで確認することができます。
【参考サイト】中小企業庁:認定経営革新等支援機関検索システム
2-2.必要書類
- 応募申請書
- 事業計画書
- 認定支援機関による確認書
- 再生計画策定にかかる証明書
- 認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業に係る確認書
3.申請すれば交付されるものではない
事業承継補助金が実際に交付されるのは、審査に通った一部の申請者です。
過去の実績における申請者に対する採択者の割合は、2016年で約5%、2017年で約12%となっており、事業承継補助金は狭き門なのです。
3-1.採択されるためのポイント
この狭き門をくぐるためには、申請までの事前準備がカギとなってきます。
採択される可能性を上げるポイントは次のような点です。これらを総合的に見て審査されていきます。
- 取り組みに独創性があるか
その企業でしか行っていないような、新たな商品やサービスが提供できることが重要です。補助金を交付して更に発展させたいという魅力があります。 - 取り組みに実現性があるか
書面に記載した取り組みが理想ではなく、実現できるものであるということを明確にしましょう。例えば、商品の仕入れ先や販売先、人員確保の方法など具体的に記載しましょう。 - 継続的な収益が確保できるか
事業収益計画には信頼性が必要不可欠です。どのような人をターゲットとしているのか、今後も安定した売上をあげるために行うことなど、時代のニーズが移り変わっていっても対応していく姿勢が重要です。
4.事業承継税制で相続税・贈与税が0に
事業承継に関する優遇制度は、事業承継補助金の他にも事業承継税制があります。
この事業承継税制とは、中小企業の非上場株式を経営者から後継者へ承継する際にかかる相続税や贈与税について、その納税が猶予及び免除される制度です。
2018年度税制改正では、事業承継税制は納税者有利な方向で大幅に改正されました。10年間の特例措置として、厳しい要件であった点が次のように改正され、より利用しやすい制度となりました。
- 対象株式数上限等の撤廃
- 雇用要件の抜本的見直し
- 対象者の拡充
- 経営環境変化に応じた減免
- 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
まとめ
事業承継補助金は借入金とは違い、返済不要の貴重な資金となります。
貰うことが難しい補助金ではありますが、今後国の予算が拡大されることになれば、それに比例して採択率も上がる可能性が考えられます。
知識を付けること、申請することに損はありませんので、要件に該当する場合には申請することをおすすめします。場合によっては、専門家へ相談することも検討しましょう。