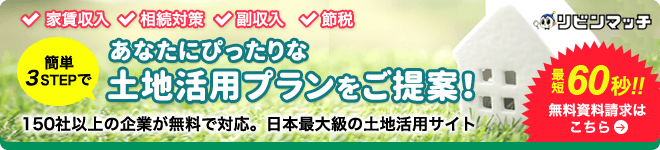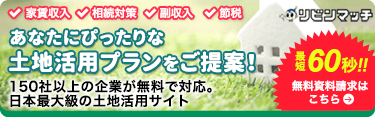不要な土地は相続放棄で手放そう
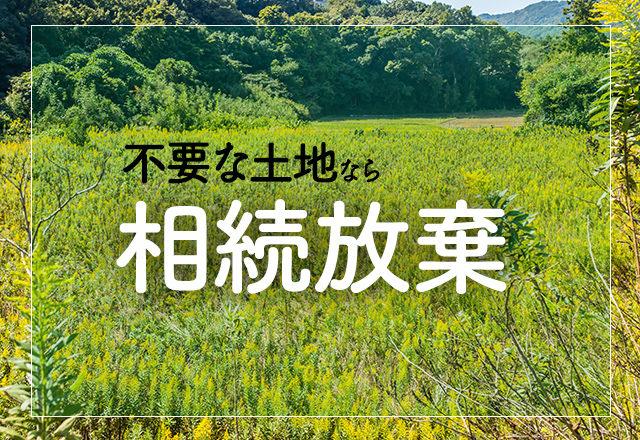
土地は時が経過しても、大きな減価をしない価値のある財産です。しかし、全ての土地がそうであるとは限りません。
中には田舎の山奥などにあり、誰も相続したくない土地、要らない土地があります。
このような土地が相続財産に含まれていた場合、相続人は泣く泣く相続するしかないのでしょうか?いえ、そんなことはありません。相続放棄という方法があります。
しかも、実はこの相続時における相続放棄が、このような利用価値のない土地を処分する数少ないチャンスなのです。
1.誰も相続したくない土地を処分する方法は?
要らない土地を処分するにはいくつかの方法がありますが、いずれの方法であっても、そう簡単に手放すことはできません。
誰も相続したくない価値のない土地であっても一度所有してしまうと、末代まで負の遺産となってしまう可能性があるのです。
1-1.要らない土地はなかなか売却もできない
不動産情報のチラシなどで、いつまでも同じ不動産が掲載されているのを見たことはないでしょうか?
利用価値のない土地を、わざわざ欲しがる人が現れるのは稀です。大規模な開発工事でも持ち上がらない限りは、買い手が付く可能性はかなり低いです。
1-2.要らない土地は寄付することも難しい
売却することができないのであれば、誰かにタダで引き取ってもらうという選択肢があります。
譲渡先としては、国や市町村といった地方公共団体、個人、法人が考えられますが、所有者が不要な土地で、更に売りに出しても誰も欲しがらない土地であるということは、これらも欲しがらないでしょう。
譲り受けてもらえるとすれば、公園にできるなどの有益な使用目的が考えられる場合や、その土地に隣接する土地の所有者が1つの土地として使用したい場合などでしょう。
1-3.要らない土地でも所有権は放棄できない
民法には、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と定められており、持ち主のいない土地は国の財産になります。 それならば、土地の所有権を放棄すれば自動的に国に所有権が移るのではないでしょうか?
結論は、できません。土地の所有者がその所有権を一方的に放棄することはできないため、その登記方法もありません。
2.要らない土地は相続放棄で手放せる
土地は、相続放棄をすることで手放すことができます。ここでは、相続放棄自体や相続放棄のやり方について、説明します。
2-1.相続放棄について|相続放棄した土地はどうなる?
相続は基本的に、被相続人が所有している全ての財産債務を引き継ぐことになりますが、一方で相続人は「相続放棄」を選択することもできます。
相続放棄とは、財産債務の一切を相続しない方法で、家庭裁判所へ一定の手続きが必要です。
では、相続放棄した土地はどうなるのでしょうか?心配ありません。上記で解説した民法の「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」状態になります。
2-2.相続放棄をする際も考慮すべき相続順位とは
相続人は被相続人の親族ですが、親族とひと言にいっても、配偶者、両親、祖父母、子供、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、いとこなど幅があります。
そこで相続人に順位を設け、高順位の相続人から順番に相続をしていくことにより、遺産分割が円滑に進むように民法に定められています。
被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に法定相続人となります。その他の親族の順位は次の通りとなります。
- 第1順位:子供
- 第2順位:両親
- 第3順位:兄弟姉妹
相続順位は、相続放棄の際にも、注意しなければなりません。
2-2.相続放棄の申述は相続順位を考慮して行う
遺言書がなければ、被相続人の死亡によって、遺産は相続されて相続人の共有状態となります。
相続放棄をするとその相続人は始めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄をしたのが誰であるかによって法定相続人の範囲が変化し、遺産の共有関係も変化します。
よって、親族全員が相続放棄をする場合には、相続放棄の申述を何度か行う必要があります。
まず、配偶者と第1順位の子供が相続放棄の申述を行います。
すると、その相続権は第2順位の両親に移行しますので、そこでまた相続放棄の申述をします。
そして最後に、第3順位の兄弟姉妹が相続放棄の申述をすれば、親族全員の相続放棄が完了します。
このように相続権は相続順位毎に移っていくため、前もって相続放棄する旨を他の相続人に知らせておかなければ、親族間でのトラブルの原因になる可能性があるので注意しましょう。
2-3.相続放棄のやり方
相続放棄を選択するためには、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、申し立てをしなければなりません。
相続放棄の手順
- 相続放棄申述書の作成
様式は裁判所のホームページから入手できます。
【参考サイト】裁判所|相続の放棄の申述書(20歳以上) - 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の管轄先)に必要書類を提出
- 家庭裁判所より受理通知書が届く
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本、住民票の除票
この他、被相続人と申述人の関係性に応じて提出を求められる書類があります。
相続放棄の費用
- 収入印紙800円分
- 家庭裁判所などとの連絡用切手代
- 戸籍謄本などの書類取得費用
- 弁護士、司法書士費用(手続きの代行を依頼する場合)
2-4.相続放棄は相続に詳しい弁護士に相談を
相続放棄の手続きを説明してきましたが、実際にこれを一人でやるのは大変だと思います。
もし、「要らない土地を相続したくない」「相続放棄手続をしたい」ということであれば、自分でやらずに、相続放棄手続に精通している弁護士に依頼するのがおススメです。
事務所にもよりますが、相続トラブルに特化している弁護士事務所などであれば、数万円程度の比較的リーズナブルな費用で相続放棄を対応してくれるところもあります。
多少費用はかかりますが、手続を確実に行う上では、専門家に依頼したほうが安心です。
3.要らない土地を相続放棄する際の注意点
3-1.相続放棄をしても管理義務はある
相続放棄をしたらその時点から自動的にその土地が国の財産となり、責任から解放されるわけではない点に注意しましょう。
相続放棄後もその土地の名義人は被相続人であり、固定資産税はかからないものの、注意義務や管理義務は継続します。
3-2.相続財産管理人の選定には費用がかかる
土地の管理義務は、次の管理者が現れるまで続きます。
例えば、自分以外の相続人が相続を承認してくれればその相続人が次の管理者となります。ただ、他の相続人が相続放棄するような土地をわざわざ相続する相続人は稀でしょう。
全相続人が相続放棄をした場合には、利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求することにより、「相続財産管理人」が選任され次の管理者となります。 これによってようやく、土地の管理責任義務から解放されることになるのです。
ただし、相続放棄手続きからこの相続財産管理人選任の申し立てには、数十万円以上の費用が必要となります。
現実的にはこの負担が厳しいため、結局相続するしかなく、固定資産税の支払いと維持管理を続ける人が多くなっています。
4.相続放棄以外に要らない土地を手放す方法
費用などの問題から相続放棄も難しい場合には、次の方法を検討してみてはいかがでしょうか。
4-1.家屋が建っていれば賃貸で土地活用
その土地に家が建っている場合には、誰かに貸して賃貸収入を得る方法もあります。
収入以外にも人が住むことで家に風が通り、害虫被害や家の劣化抑えることができるメリットがあります。
「売れず、譲渡先もないような立地条件なので借りる人なんて…」と思われるかもしれませんが、都会の喧騒を離れて田舎暮らしをしたい人や、不便であっても子供を自然豊かな環境で育てたい人など、自分で所有はしたくないが賃貸で味わってみたいという思わぬ借り手が現れる可能性があります。
もっとも賃貸経営をするには責任も生じますので、管理業務は不動産会社に依頼することを検討したほうがよいでしょう。
4-2.格安で売却する
せっかく売却するのだから、より高い金額で売りたいと思うのは当然です。 しかし難あり物件の場合には、金額以外では他の不動産に勝負できないこともあります。
売り出しから3ヶ月程度経過しても動きがない場合には、思い切って売値を下げてみましょう。
4-3.広すぎる土地は分筆する
広い土地は魅力的ですが、あまりに広いと利用用途が限られてしまい需要もなくなってしまいます。
宅地や店舗、駐車場などの用途に適したサイズに分筆登記することで、ひと区画の売値も下がり、購入希望者が手を出しやすくなります。
まとめ
利用価値のないマイナスの土地は、一度所有してしまうと手放すのがなかなか難しいのが現状です。
また、このような土地が遺産に含まれる場合には、遺産分割協議などそれに付随してさまざまな問題が発生する可能性がありますので、税理士、弁護士、司法書士など適切な専門家に相談するようにしましょう。