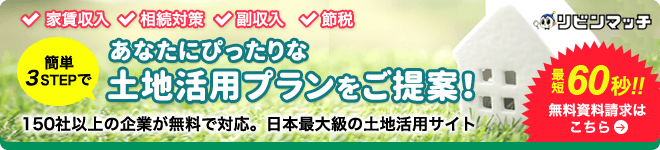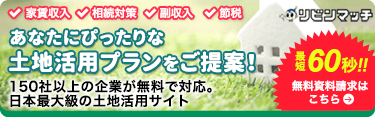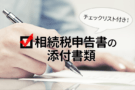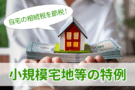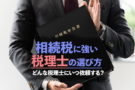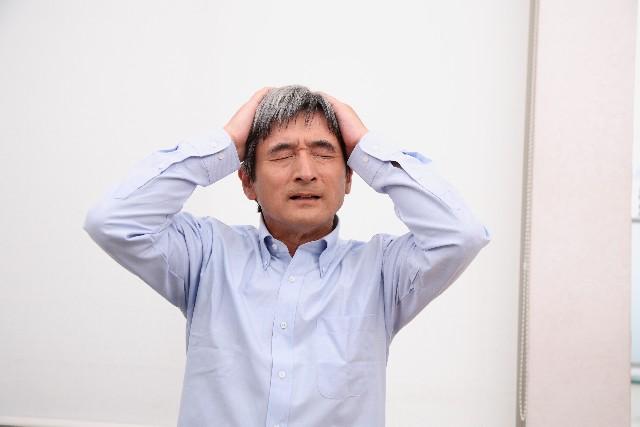相続した資産に事業用資産の買換え特例を利用しよう

「相続した事業用地や事業用建物の収益や利回りが良くない」と感じている方も多いと思います。
そこで、今回は、相続した事業用資産を有効活用するための方法として、「事業用資産の買換え特例」について解説していきます。
1.事業用資産の買換え特例とは
事業用資産の買換え特例とは、個人が事業用の土地建物等を譲渡してその代わりに資産を取得し、一定の要件を満たせば、譲渡益にかかる譲渡所得税(所得税と住民税)の一部について、課税を将来に繰り延べることができる特例です。
所有する事業用の土地や建物を一定の条件下で買い替えることにより、譲渡所得税の節税が期待でき、相続税の節税対策にも効果的です。
ただし、あくまで課税の繰り延べであり、譲渡所得税が非課税となるわけではありません。
2.事業用資産の買換え特例の適用要件
事業用資産の買い替え特例を適用するには、以下7つ全ての要件を満たす必要があります。
2-1.譲渡資産・買換え資産とも事業用であること
譲渡する土地建物等が事業に使われており、代わりに取得する資産も事業に使うことが必要です。
特例の対象となる事業には、農業、製造業、小売業などが挙げられ、賃貸マンションや駐車場など不動産の貸付けも含まれます。
【参考】国税庁HP No.3402 事業用の資産の範囲
2-2.譲渡資産と買換資産が一定の組合せに当てはまること
譲渡資産の買換え特例の適用を受けるには、譲渡資産と買換え資産とが一定の組み合わせになっていなければなりません。
定められた組み合わせは10通りになりますが、譲渡資産と買換資産の最も一般的な組合せとして、次の例を挙げることができます。
| 譲渡資産 | 買換資産 |
|---|---|
| 譲渡の年の1月1日において、所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物や構築物等 | 国内にある事業用の土地や建物等。ただし、土地の場合は、その面積が300㎡以上のものに限る |
この他の組み合わせは、特殊なケースと言えるでしょう。
2-3.取得する土地の面積が譲渡する土地の5倍以内であること
買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、譲渡した土地の面積の5倍以内である必要があります。
ただし、5倍を超えると特例がすべて適用されないわけではなく、5倍に相当する金額には特例が適用され、5倍を超える金額には特例が除外され、通常の20%の譲渡所得税が課税される仕組みです。
2-4.譲渡資産の売却前後1年以内に買替資産を取得をすること
資産を譲渡した年か、その前年、あるいはその翌年に買換資産を取得する必要があります。
譲渡の前年に取得した資産を買換資産とするためには、取得した翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出する必要があります。
また、譲渡した翌年に買換資産を取得する予定の場合には、譲渡した年の確定申告の際に、「買換(代替)資産の明細書」を提出する必要があります。
2-5.買換え資産購入後、1年以内に事業に使うこと
買い換えた資産をその資産の取得日から1年以内に事業に使う必要があります。
2-6.贈与/交換などでないこと
特例の対象は、買い替えであり、贈与や交換など売買でないものは対象になりません。
2-7.譲渡する資産の所有期間が5年を超える
譲渡する資産は、原則として譲渡する年の1月1日時点での所有期間が5年を超えている必要があります。
3.事業用資産の買換え特例の効果
課税される譲渡益は、原則、譲渡益(収入金額)の20%です。
原則として、譲渡益の80%分は繰り延べられますが、地方から都心の物件に買い換える場合には、繰り延べ割合が75%や70%に引き下げれる場合があります。
【参考】国税庁HP No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
3-1.譲渡額≦取得額の場合に課税される譲渡所得額
課税対象となる譲渡所得金額の計算は、課税割合が20%の場合次の通りです。
- 課税される譲渡所得金額=収入金額(譲渡額×20%)ー必要経費{(譲渡資産の取得額+譲渡費用)×20%}
譲渡額≦取得額の場合の事例
次の事例で特例の効果を見ていきましょう。
事例1.
- 相続した資産の譲渡額:1億万円
- 譲渡資産の取得額:6,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 買換資産の取得額:12,000万円
課税される譲渡所得額=譲渡額1億円×20%ー(譲渡資産の取得額6,000万円+譲渡費用200万円)×20%=760万円
譲渡所得税額=760×20%=152万円
一方、特例の適用がなければ、課税対象となる譲渡所得額と税額は、以下の通りです。
課税される譲渡所得額=譲渡額1億円ー(取得した資産額6,000万円+譲渡費用200万円)=3,800万円
譲渡所得税額=3,800万円×20%=760万円
上記のことから、特例の適用を受けることで、760万円-152万円=608万円も減額できることがわかります。
3-2.譲渡額>取得額の場合に課税される譲渡所得額
課税割合が20%の場合に、課税される譲渡所得額は、次の計算で求めます。
- 課税される譲渡所得額= 収入金額{譲渡資産の譲渡額ー(買換資産の取得額×80%)}ー必要経費{(譲渡資産の取得価格+譲渡費用)×(収入金額÷相続した資産の譲渡額)}
譲渡額>取得額の場合の事例
次の事例で特例の効果を見ていきましょう。
事例2.
- 相続した資産の譲渡額:1億6,000万円
- 譲渡資産の取得額:6,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 買換資産の取得価格8,000万円
課税される譲渡所得額=収入金額{譲渡額1億6,000万円ー(買換資産の取得額8,000万円×80%)}ー必要経{(譲渡資産の取得額6,000万円+譲渡費用200万円)×(収入金額9,600万円÷譲渡額1億6,000万円)}=5,880万円
譲渡所得税額=5,880万円×20%=1,176万円
一方、特例の適用がなければ、課税対象となる譲渡所得額と譲渡所得税額は、次の通りです。
課税される譲所得額=譲渡額1億6,000万円ー(譲渡資産の取得額6,000万円+譲渡費用200万円)=9,800万円
譲渡所得税額=9,800万円×20%=1,960万円
上記の通り、事業用資産の買換特例を適用すれば、1960万円−1176万円=784万円も減額できることになります。
4.事業用資産の買換え特例の申告手続き
ここでは、この特例を利用する場合の手続き(必要書類や期限など)を、ケースごとに説明します。
4-1.資産の譲渡と取得を同一年度にする場合
次の書類を添付し、確定申告することが必要です。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 買換資産の登記事項証明書などその資産の取得を証する書類
- 譲渡資産及び買換資産が特例の適用要件とされる特定の地域内にあることを証する市区町村長等の証明書など
4-2.資産譲渡の前年に取得する場合
資産譲渡の前年に取得した資産を買換資産とするためには、取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出します。
4-3.資産譲渡の翌年に取得する場合
譲渡した翌年に買換資産を取得する予定の場合には、譲渡した年の確定申告書を提出する際に、取得する予定の買換資産について「買換(代替)資産の明細書」を提出します。
翌年に取得する場合の手続きは、次のようになります。
- 確定申告書に「買換(代替)資産の明細書」を添付
- 記述される取得価額の見積額に基づいて譲渡所得の計算して納税
- 買換資産を実際に取得した清算を行う
- 清算結果の税額が減少 → 更正の請求し、所得税の還付を受ける
- 清算結果の税額が増加 → 修正申告
4-4.期限までに買換資産を買えなかった場合
やむを得ない事情で、資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得できない場合には、譲渡年の翌年12月31日後から2年以内で税務署長が認定した日まで、買換資産の取得期間を延長することができます。
やむを得ない事情とは、次のようなケースです。
- 工場などの敷地の造成や建設移転にかかる期間が通常1年を超えること
- 法令の規制等により取得計画の変更をしなければならなくなったこと
- 売主、その他の関係者との交渉が長びき、簡単に資産の取得が出来ないこと
- 上記3つの条件に準じた事情があること
買換資産の取得期間の延長を受けたいときは、資産を譲渡した年の確定申告の際に、「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」を税務署長へ提出します。
5.事業用資産の買換え特例の注意点
5-1.相続した土地建物の取得日
相続した土地や建物の場合には、被相続人がそれらの資産を取得した日をそのまま承継することになります。
したがって、被相続人が取得した時から、相続で取得した人が譲渡する年の1月1日までの年月が所有期間となり、長期譲渡所得か短期譲渡所得かが判断されます。
5-2.相続した土地・建物の取得費
相続した土地や建物は、被相続人がそれらの資産を取得した際に支払った購入費をそのまま承継します。
被相続人が事業用資産の買換え特例を利用していた場合には、「買換資産の取得費」を引き継ぎます。
ただし、建物に特例の適用を受けると、費用として計上できる減価償却費が小さくなるため、見かけの利益が増え、結果として所得税、住民税の負担増になるのはデメリットと言えるでしょう。
5-3.譲渡資産・買換え資産の所有者
特例を受けるためには、譲渡資産も買換え資産も所有者自身の事業用に使われている必要があります。
しかし、売る資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合には、所有者本人の事業に使われていたものとして取り扱うことができます。 また、買換えた資産についても同様です。
まとめ
「事業用資産の買換え特例」は、事業をやめて資産を売却しない限り、半永久的に繰り延べができるため、事業継続の観点で、メリットのある特例と言えます。
適用を受ける際には、要件の判定や、特例利用時の収支シミュレーション等を実施する必要があり、専門知識が必要になります。
信頼のおける相続に強い税理士に相談することをお勧めします。