準確定申告書と付表の書き方(記入例つき)
確定申告をせずに被相続人が亡くなった場合、相続人が代わりに行うのが準確定申告です。準確定申告が必要な場合から準確定申…[続きを読む]
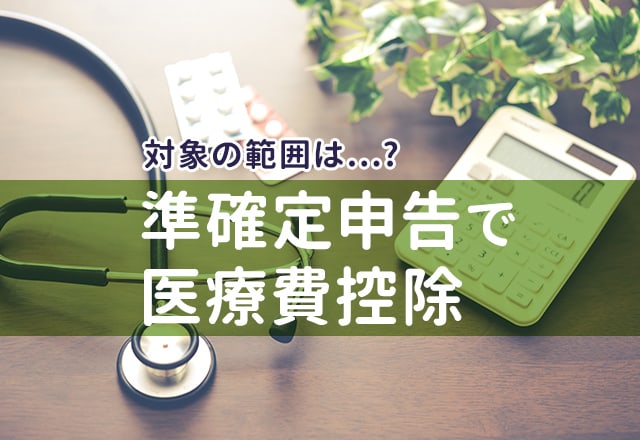
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の確定申告(被相続人)のことをいい、対象となる所得は被相続人の1月1日~死亡日までの所得です。
亡くなった父や母、配偶者などの医療費控除を受けたいと考えている方は、準確定申告で控除を受けることができます。
ただし、既に亡くなった人の医療費であるため、申告の対象になるかどうか判断が難しいことがあります。今回は準確定申告における医療費控除について、医療費の具体的なケースを含め解説します。
なお、準確定申告書の書き方については、次の記事をご一読ください。
医療費控除とは所得控除の1つで、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身や家族のために支払った医療費の合計が10万円(※)を超える場合に、適用を受けることができる制度です。
医療費控除は年末調整で受けることはできません。税務署へ確定申告することで治療費の一部が減税される形で返ってきます。
(※)所得が200万円未満の場合は、その所得金額の5%の金額
準確定申告での医療費控除を判断するポイントは、被相続人が実際に支払った医療費であるかという点です。
被相続人が支払った医療費は対象となりますが、相続人が支払った医療費は対象外です。
2つ目のポイントは、死亡日までに支払った医療費であるかという点です。
被相続人が死亡後に自らの医療費を支払うことは不可能なので、当然対象外となります。
では、準確定申告の対象と医療費とは、どのようなものなのでしょうか?
被相続人が死亡した後に、被相続人と同一生計の相続人が支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象となります。更にこの場合には、相続税計算における債務控除にも含めることができます。
これに対して、被相続人と相続人が同じ生計でなければ、相続人が支払った医療費は、控除の対象外です。
生計を一にするとは、簡単に言うと、被相続人と相続人の日常生活での財布が一緒であったということです。
例えば、夫婦共働きで、共に収入があったとしても、日常の生活費を互いの収入から工面しており、夫が亡くなった場合には、妻は夫と生計一だったということができます。
準確定申告の医療費控除の対象は、死亡日当日まで含みます。
また、医療費控除の対象になるかどうかは死亡日が境となっています。
例えば、病院で亡くなった当日、すぐに入院費を支払えば準確定申告の対象となり、後日支払うと対象になりません。
高齢者によくある医療費の具体例を挙げて、対象となるかどうかを確認していきましょう。
死亡診断書代は、医療費控除に含めることはできません。一方で、相続税を計算するときに、債務として控除することはできます。
死亡診断書の費用は、死亡日までの病院の入院費に含まれていることがあるので、医療費控除の申告の際には注意しましょう。
入れ歯治療は保険適用外の入れ歯であっても医療費控除の対象となります。
しかし、入れ歯安定剤は治療のための費用ではなく、日常生活のための費用なので対象外です。
育毛剤や育毛外来治療にかかる費用は、例え医師によって処方されたものであっても医療費控除の対象となりません。
育毛行為は美容目的として扱われるため、命にかかわるものではないということが理由です。
医師の診療を受けて、糖尿病治療のために提供されたインシュリン注射器に限り医療費控除の対象となります。
おおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にある、または、寝たきり状態にあると認められる人に必要となるオムツ代が対象となります。
全てのオムツ代が医療費控除の対象となるわけではありません。
控除を受けるためには、医師から発行してもらった「おむつ使用証明書」と領収書を確定申告書に添付する必要があります。
【詳細】厚生労働省HP おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省の認定を受けた、温泉を利用した健康づくりをすることができる施設のことをいいます。
医師が治療のために温泉療養を行わせた旨を「温泉療養証明書」により証明すれば、施設利用料や施設までの交通費が医療費控除の対象となります。
控除を受けるためには、医師が発行した「温泉療養指示書」と領収書を確定申告書に添付する必要があります。
介護は医療ではないため、介護用ベッドの購入費やレンタル料は医療費控除の対象になりません。
介護費、食費、居住費としてのサービス対価は医療費控除の対象となりますが、日常生活費や特別なサービスへの対価については対象となりません。
日常生活費とは、理美容代や施設から提供されるサービスのうち、日常生活で必要とされるものの費用で、入居者が負担するのは当然と考えられる費用のことをいいます。特別なサービスとは、施設で希望者のみで行われるクラブ活動などにかかる費用のことをいいます。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
【詳細】国税庁HP №1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
デイサービスのために施設へ通う際に支払う費用で、通常必要となる交通費も医療費控除の対象になります。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設への介護費、食費、居住費としてのサービス対価は、その2分の1の金額が医療費控除の対象となります。日常生活費や特別なサービスへの対価については対象となりません。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
有料老人ホームの利用料は医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となる施設は、上記で紹介した、次の施設の限られます。
医療費控除の対象になる金額は、通常の確定申告での医療費控除の計算と同じく、次の計算式で求めることができます。
したがって、確定申告と同様に、医療費控除の最高限度額は200万円であり、200万円までが被相続人の課税所得額から控除することができる金額です。
被相続人の所得によって、次の2つに分かれます。
①被相続人が亡くなった年の所得が200万円以上の場合
実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額− 10万円=医療費控除の金額
「保険金などで補填される金額」には、「生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金」などが該当します。
また、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きし、引ききれない金額が生じた場合には、他の医療費から差し引くことはできません。
②被相続人が亡くなった年の所得が200万円未満の場合
実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額− 総所得額の5%=医療費控除の金額
医療費控除を受けるためには、準確定申告書の第一表・第二表と、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入のうえ、添付して提出する必要があります。
ただし、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせなど)」があれば、医療費控除の明細書の「1 医療費通知に関する事項」の指定欄に、通知に記載されている被相続人が負担額した医療費の合計額を記載して、医療費控除の明細書の記入を省略化できます。この場合には、医療費通知も添付します。
医療費の領収書は、準確定申告書に添付する必要はありません。しかし、税務署が医療費の内容を確認するために必要となることがあり、相続人は、領収書を5年間保存しなければなりません。
医療費控除の明細書の書式は、以下のサイトからダウンロードが可能です。書き方については、以下のPDFを参考にしてください。
なお、準確定申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出しますが、郵送による提出の他、2020年以後分は「e-Tax」で送信することもできます。
【医療費控除の明細書書式】|国税庁
【準確定申告書・医療費控除の明細書の書き方】|国税庁
ここまでに解説した通り、準確定申告の医療費控除の対象となるかどうかは、医療費を支払ったのタイミング、支払った人などの要因により変わってきます。以下の表に簡単にまとめましたので、ご確認ください。
| 支払った人 / 支払った期限 | 死亡前 | 死亡後 |
|---|---|---|
| 被相続人 | 準確定申告の医療費控除 | ― |
| 相続人(生計一の親族) | 相続人の確定申告の医療費控除 | |
| 上記以外 | 医療費控除対象外 | |
医療費控除自体の対象となるかどうかの基本的な考え方は、その費用が治療を目的とした医療費であるかです。医療費ではありませんが、治療を受けるための交通費も対象となります。
美容整形や予防接種、サプリメント購入などは治療を目的としたものはなく、美容や病気予防、健康増進のものであり医療費ではありません。ただし、これらの費用であっても医師が治療目的と認めたものについては、医療費控除が認められる場合があります。
老人ホーム関連費用については、国税庁において対象となる施設や対象となる居宅サービスが明確に定められています。また、これらに該当する施設が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されています。
判断に迷う場合には、税務署に直接確認しましょう。あやふやな自己判断で申告するよりも、申告先の税務署に確認すると安心です。