特別受益と寄与分がある場合の相続税について分かりやすく解説!
特別受益や寄与分は、相続人間の公平を図るための制度ですが、これらがある場合、相続分の計算方法も通常とちょっと変わりま…[続きを読む]
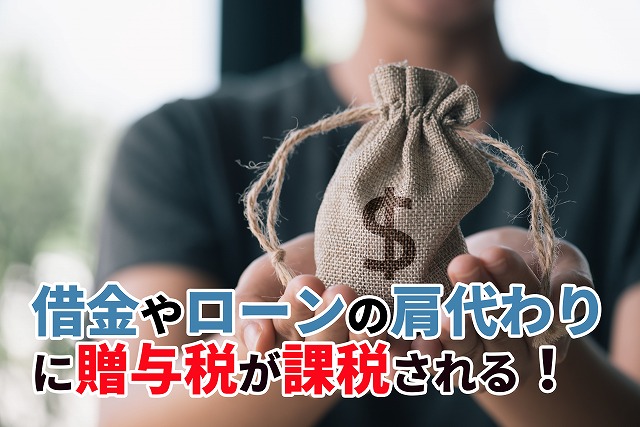
借金やローンなどを肩代わりしてもらった場合にも、肩代わりしてもらった額に対して贈与税がかかることをご存じでしょうか?
思わぬところで贈与税が発生することがあり、注意が必要です。
今回は、借金やローンなどの肩代わりに発生する贈与税と、贈与税を発生させないためにできることについて解説します。
目次
「何も貰っていないのにどうして贈与税がかかるのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。まずは、借金の肩代わりがなぜ贈与税の課税対象になるのかについて解説します。
借金や税金を肩代わりしてもらうことは、お金を贈与されて返済したことと同じ理屈になり、贈与税が課されるのです。
贈与者(贈与した側)が受贈者(贈与された側)を通さずに直接返済した場合であっても、借金分のお金を贈与されたことと等しいことになります。したがって、肩代わりしてもらった受贈者が贈与税の課税対象になってしまいます。
ただし、債務者が借金苦で著しい債務超過状態であり、貯蓄もなく日々の生活に困っているような、明らかに自力では返済出来ないような場合には、親や親族などが肩代わりしても贈与税はかかりません。
個々の状態により判断されるため、すべてが返済不可能な状態として認められるわけではない点にはご注意ください。
また、肩代わりしてくれた人の相続が発生した場合には、この贈与は特別受益になる可能性があります。
特別受益とは特定の相続人が被相続人から特別に得た利益のことをいいます。
相続人間の不公平を調整するために、相続税の計算時には特別受益を受けた相続人は法定相続分から贈与額を控除して分配することになります。
思いがけず贈与税の課税対象になってしまう「肩代わり」には、次のようなものが挙げられます。
肩代わりを検討されている場合には、事前に十分な確認を取るように注意してください。
相続税は、相続人それぞれが相続した財産額に応じて納める税金です。
相続税の肩代わりに贈与税が発生するよくあるケースは、相続人の1人が他の相続人の分もまとめて支払ってしまうパターンです。
例えば、兄弟姉妹4人が遺産を相続してそれぞれに相続税が発生したが、長男が遺産を最も多く相続したからと、全員分の相続税を支払った場合には、支払ってもらったそれぞれの相続人には贈与税がかかります。
退職金などまとまった額の資金を得ることができたタイミングで、子供の奨学金を一括返済や、繰り上げ返済をしてあげたいと考える親は多いでしょう。
親には子供の教育費を負担する義務があり、必要な金額についてはいくらであっても贈与税はかからないため、奨学金も同様に捉えてしまいっている方は少なくないかもしれません。
しかし実は、奨学金は子供が自分の名義で借りている借金であることから、教育費ではなく子供個人の借金とし扱われるため、親が奨学金の肩代わりをした場合には子供に贈与税がかかります。また、教育資金には該当しないため、親が一括返済したとしても、教育資金の一括贈与の非課税制度も使うことはできません。
子供を受取人にして親が肩代わりして支払ってきた生命保険が満期になり、子供に保険金が支払われた場合にも、親が貯めてきたお金を子供へ贈与したとして扱われ、満期保険金相当額の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
例えば、親が子の肩代わりをして500万円払い込んできた保険の満期保険金600万円が子供に振り込まれた場合には、600万円に対して贈与税がかかります。
住宅ローンは、借入を行った名義人が返済しなければなりません。
夫の名義である住宅ローンを妻が肩代わりして返済したり、子供の名義である住宅ローンを親が肩代わりして返済したりすると、返済分は贈与税の課税対象になります。
この他に考えられるケースとしては、夫婦で共働きをしながら連帯債務で住宅ローンを組む場合です。住宅を購入するときには共働きであったのに、妊娠出産によって妻が退職したために妻分の返済も夫が行うようになると、その返済分については贈与の扱いになって贈与税が発生します。
この場合には、夫婦の連帯債務から、夫単独のローンへと借り換えをした場合にも、贈与税が発生する可能性があります。
肩代わりすると贈与になるため貸付にする場合には、返済期間や利息の設定をしていないと、実質的には贈与であるとみなされてしまい貸付金額が贈与税の対象になります。
また、借主の返済能力に対して過大な貸し付けが行われている場合にも贈与税がかかります。例えば、長年無職で安定収入がない子に対して親が1,000万円貸し付けたとしても、返せる当てがないからです。
最後に、返済はしているけれども無利子であるという場合には、借主は利子を払わないという利益を貸主から得たということになり、その利益相当額に対して贈与税が発生する可能性があります。
新社会人などにはよくある話ですが、車を買いたいけれど貯金もないし自動車ローンも難しいという場合に、親から借金をすることがあります。
この借金の残高について、「もう返さなくていいよ」と返済の免除をした場合には、本来返済すべき金額分の利益を得たことになり、残高分の贈与があったものとして贈与税がかかります。
それでも借金を肩代わりするという方のために、贈与税を課税させない、または軽減させる方法を最後にご紹介します。
暦年贈与の基礎控除額である年間110万円までの贈与は、非課税となります。
1月1日から12月31日までの間に行われた贈与が110万円以下であれば、贈与税はかからないため、肩代わりする額を調整すると良いでしょう。
また、2024年の1月1日以降は、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円以下の贈与には贈与税も相続税も発生しないことになるため、同じ効果が得られます。一方で、同日からは暦年贈与を利用すると、生前贈与加算が3年から7年に延長されます。詳しくは、以下の記事をご一読ください。
肩代わりしたお金を返せば、貰ったことにはならないため、贈与ではなく貸付として取り扱われます。
そのためには、お金を借りる契約である「金銭消費貸借契約」を結ぶ必要があります。
ただし、貸付金は貸主の財産である点は忘れないでください。
いずれ貸主の相続が発生した際には、貸付金の残高は相続財産となり、相続税の対象になります。金額によっては贈与税を支払った方が安かったということもあり得ます。事前に税理士へ相談することをおすすめします。
金銭消費貸借契約として認められるためには、金銭消費貸借契約書を作成しておくことが有効です。契約自体は借主と貸主の口約束でも成立しますが、それだけでは税務署へ証明する手段がありません。必ず金銭消費貸借契約書を作成するようにしましょう。
その他には、実際に返済すること、銀行振り込みで返済の証拠を残すことで貸付であることを強固に証明することができます。
不定期な返済や出世払いは認められませんので注意してください。
負担付贈与で贈与税の課税対象となるのは、贈与財産の価額から負担額を控除した価額となります。したがって、単に財産を贈与した場合に比べて贈与税の額を抑えることができます。
例えば、夫婦の連帯債務型住宅ローンを、夫の単独ローンに借り換える際に、妻の住宅の持分を夫名義に書き換えて負担付贈与にすれば、住宅ローンの残債を住宅の金額から差し引いた額が贈与税の課税対象となります。
ただし、この場合には、不動産を時価(市場化価格)で評価し贈与税が計算される点や、また登記に要する登録免許税や、譲渡所得税が発生する点など、考慮しなければならないポイントが複数あります。
検討したい場合には、事前に税理士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
住宅ローンの場合の名義人の変更には、貸主であるローン会社や金融機関などの承諾が必要と契約で定められていることが一般的です。
承諾を得ることは難しいとされていますが、ダメもとで確認してみる価値はあります。
カードローンの場合には、氏名変更など本人以外への名義変更はできません。その理由は、カードローンは、融資する人個人の支払い能力や過去の返済実績に基づいて審査し、融資しているからです。
贈与になると認識せずにした贈与は、高額である場合が多く、贈与税は税率が高いため、とんでもない税額が突然発生するということになりかねませんので注意が必要です。
借金の肩代わりを検討している場合には独断は禁物です。貸付とする場合にも計画的な準備が重要になりますので、まずは相続税に強い税理士にお問い合わせください。