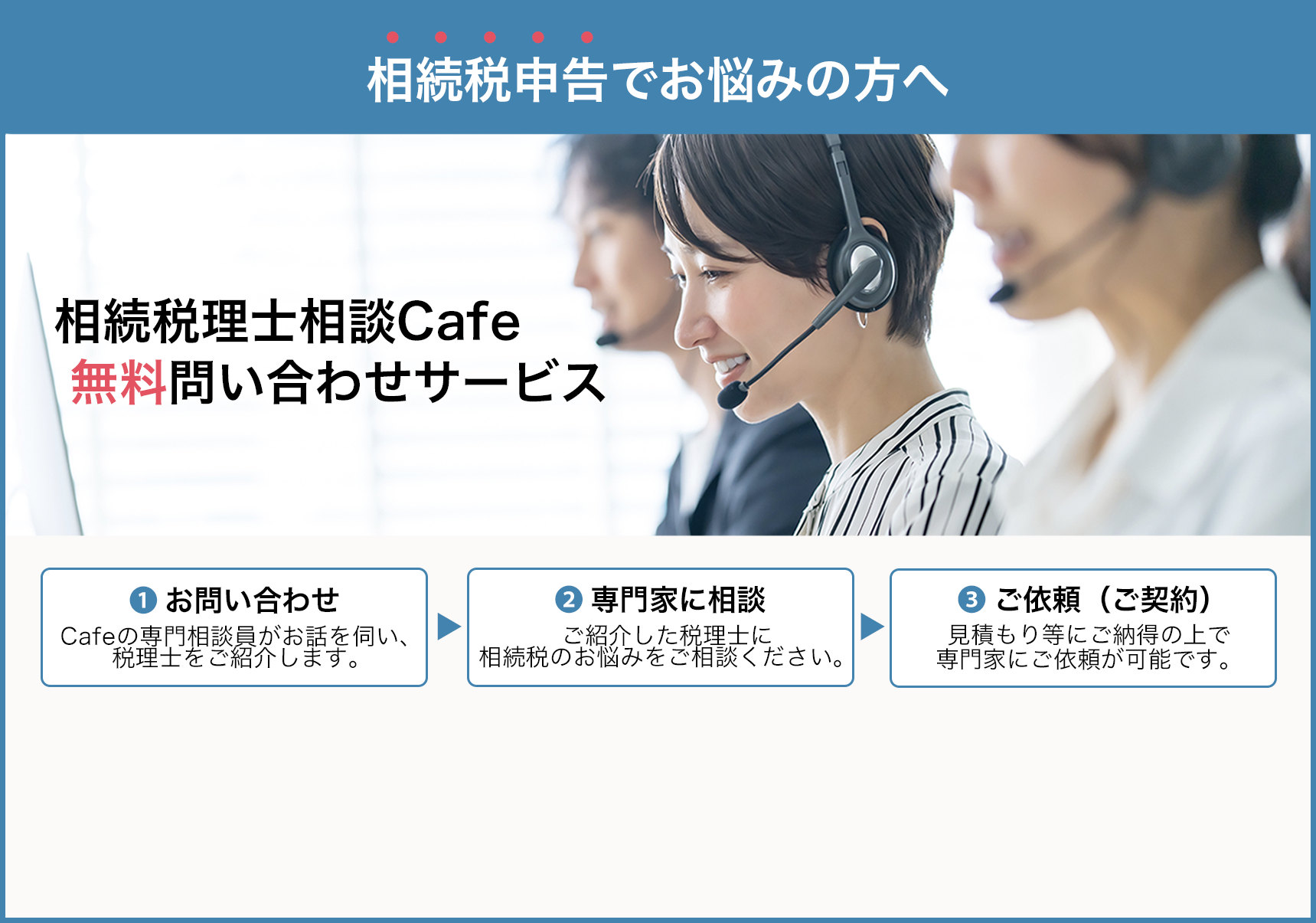相続税の按分割合について|端数処理で相続税の節税は可能?

相続税の計算には「按分割合」を用いて、各相続人の相続税額を計算します。
この按分割合の端数処理は意外にも重要であり、0.001の差でも相続財産額によっては、相続税額が数十万円変わることもあります。
今回は、相続税の按分割合について詳しく解説していきます。
目次
1. 相続税の按分割合ってどんなもの?いつ使う?
まずは相続税の按分割合についての基本を解説します。
1-1.相続税における按分割合とは
相続税における按分割合とは、相続税をどのくらい負担するかを調整した割合のことをいい、次の算式で計算されます。
按分割合=各相続人の課税価格 ÷ 課税遺産総額
例えば、課税遺産総額が9,000万円で、2人の子供が2分の1ずつ相続した場合には、「4,500万円÷9,000万円=0.5」となり、按分割合は0.5ずつということになります。
しかし、実際の相続税計算において按分割合は割り切れないことがほとんどであり、1人の子が3,000万円、もう一人が6,000万円を相続した場合には、3000万円を取得した相続人の案分割合が「3,000万円÷9,000万円=0.33333333…」、6,000万円を取得した相続人の按分割合が「6,000万円÷9,000万円=0.666…」となります。
この端数処理が今回のテーマです。
1-2.相続税で按分割合が必要なタイミング
それでは按分割合は実際の相続税の計算過程において、どの部分で必要になるのでしょうか。計算の流れを簡単に見ていきましょう。
正味遺産総額を計算する
プラス財産から借金などの負債であるマイナス財産を差し引き、正味の遺産総額を計算します。
プラス財産ーマイナス財産=正味の遺産総額
課税遺産総額を計算する
正味遺産総額から基礎控除を差し引き、相続税の課税対象となる課税遺産総額を計算します。
正味の遺産総額ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
相続税の総額を計算する
法定相続分で分割した場合における各相続人の相続税を計算し、それを合算して相続税の総額を計算します。
課税遺産総額×法定相続分=各人の法定相続分に応じた相続税額
相続人Aの法定相続分に応じた相続税額+相続人Bの法定相続分に応じた相続税額・・・=相続税の総額
按分割合によって各相続人の相続税を計算する
各相続人が実際に相続した財産額に応じて、相続税の総額を分けます。
ここで按分割合を使用します。
相続税の総額×実際に相続した財産額の割合=各人の実際の相続税額
各種の加算控除を行う
配偶者の税額軽減や未成年者控除など、それぞれの相続人ごとに相続税の加算や控除を行い、納付すべき相続税額を確定させます。
2.相続税における按分割合の端数処理
前述した通り、按分割合は割り切れないことがほとんどです。
よって、端数処理の方法は法令解釈通達に定められており、相続人全員の同意がある場合には、小数点以下第2位未満については調整できるとされています。
ただし、割合の合計は必ず「1.00」にしなければなりません。
例えば、相続人が3人おり、Aが0.33333333…、Bが0.45357833…、Cが0.2138834…であった場合には、「A:0.333、B:0.450、C:0.217」でも、「A:0.332、B:0.455、C:0.213」でも良いということです。
【参考サイト】第16条《相続税の総額》関係|国税庁
3.相続税の按分割合は節税に使える
按分割合の端数処理は小さな数値ではありますが、母体の大きい相続税では何十万もの節税になることがあるのです。
小数点以下第2位未満については、単に切り捨て、切り上げ、四捨五入するのではなく、いくつものシミュレーションを経てから決めましょう。
3-1.小数点以下第2位未満の恣意的な調整で節税できる
相続税の申告書には、按分割合は10桁まで記載できるようになっており、10桁で計算する方が各相続人の相続税額を限りなく公平にすることはできます。
しかし、相続税が軽減できる各種の特例や控除は、利用できる相続人が限られることから、他の相続人に比べて利用できる特例や控除が少ない相続人については、按分割合を少なくすることで相続税の節税に繋げることが可能です。
国に多くの相続税を納めても何の得もありません。納付税額の平等性よりも、全相続人の相続税の総額を重視された検討をおすすめします。
3-2.端数処理で相続税の総額を下げる方法
端数処理の調整によって、具体的にどのくらい節税できるのかを見てみましょう。
【例】
- 課税遺産総額:1億4,000万円
- 相続人:妻、長男
- 相続分:妻1億円、長男4,000万円
- 相続税の総額:1,560万円
まず按分割合を単に四捨五入した場合です。
按分割合
妻 :1億円÷1億4,000万円=0.71428571… → 0.714
長男:4,000万円÷1億4,000万円=0.28571428… → 0.286
各相続人の相続税額
妻 :1,560万円×0.714=11,138,400円
長男:1,560万円×0.286=4,461,600円
妻は、「配偶者の税額軽減」によって1億6,000万円までの相続財産については相続税がかからないため、相続税は0になります。長男には特に控除がなかったとすると、長男の相続税額は4,461,600円ということになります。
次に、按分割合を恣意的に調整してみましょう。
妻は配偶者の税額軽減によって相続税は0になることを考慮すると、できるだけ配偶者に相続税を集めた方が良いということになります。
按分割合
妻 :1億円÷1億4,000万円=0.71428571… → 0.719
長男:4,000万円÷1億4,000万円=0.28571428… → 0.281
各相続人の相続税額
妻 :1,560万円×0.719=11,216,400円
長男:1,560万円×0.281=4,383,600円
この場合の相続税は4,383,600円ということになり、按分割合を四捨五入した場合の4,461,600円よりも78,000円も少なくなりました。
小数点以下第2位未満のたったこれだけの調整で、78,000円も節税できるのです。
税理士に按分割合のシミュレーションをいくつも出してもらい、相続人全員で相談して決めると良いでしょう。
まとめ
相続税の按分割合は、各相続人の相続税額を計算する際に使用する割合で、小数点以下第2位未満については恣意的な調整が認められています。
相続税はわずかな差で数十万円もの差が出る世界であるため、入念なシミュレーションが重要になります。
ただし、単に節税だけの問題ではなく、相続人間の公平性を重視したい相続もあるでしょう。按分割合については専門知識が必須になります。必ず税理士に相談し、主導してもらいながらそれぞれの相続に合った最適値を決めましょう。