相続税の税務調査の時期はいつ?税理士立会で断然有利に!
相続税の税務調査の時期がいつで、どのような内容でどこまでチェックされるのか、どのような対策をしておけばよいのか解説し…[続きを読む]
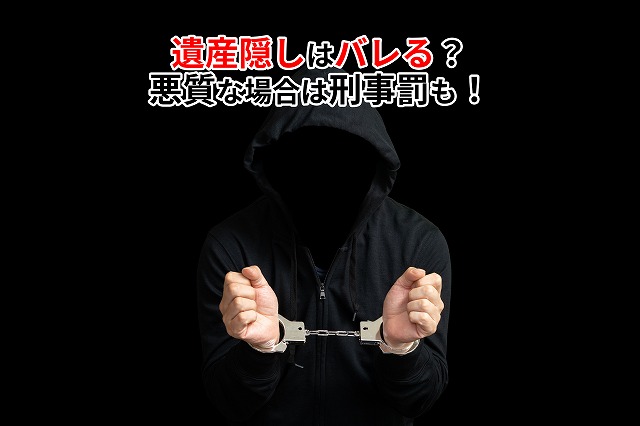
誰でも税金は払いたくないものです。特に相続税は、2015年に基礎控除が変更になって以来、下限に2,400万円もの差が出ており、相続税の課税対象者は増えています。
では、遺産を隠して相続税を申告してもバレないのでしょうか?
絶対にバレるとは言い切れませんが、残念ながら、ほとんどの場合バレてしまいます。
ここでは、税務署に遺産隠しがバレる理由や、バレるとどのようなペナルティ・罰があるのか、他の相続人に遺産を隠されないための対策などをご紹介します。
目次
最初に、なぜ税務署に遺産隠しがバレるのかを解説します。
税務署には、想像以上に巨大な調査権限があります。
国税庁は、全国の国税局・税務署をネットワークで結び、あらゆる税金の申告・納税事績や各種情報を入力した国税総合システム(通称KSK)を運用しています。これにより、税務署は、被相続人の収入や、どのような財産を取得・相続したかを把握することができます。
また、銀行や信金などの金融機関では、亡くなった方の預金口座の残高や、過去の全明細を提出させ、残っている入・出金伝票を見て印鑑や筆跡を調査することができます。
本人の口座だけでなく、配偶者・子ども・親戚など関係者の口座を調べることもでき、金融機関に拒否権はありません。
株式や保険金についても同様です。
不動産については、税務署が毎月法務局から登記情報を取得しており、不動産の所有者が移転すれば、税務署の知るところとなります。
また、税務署には、相続税についても税務調査の権限を有しており、相続人などに対して直接徹底的に調査することができます。
税務署は、少しでも多く、確実に税金を徴収するために日夜努力を重ねています。
脱税の手口などの過去事例が蓄積されており、どんなところから切り込んでいけば隠し財産が見つかるか、どんな場合に脱税が行われるか、徹底的に研究しつくしているプロフェッショナル集団です。
では、遺産隠しがバレるとどのようなペナルティや罪があるのでしょうか?
相続人が相続財産を処分したときには、単純承認がみなされ、相続放棄をすることができません(民法921条1号)。
「処分」には、相続人が自分のものとして遺産を売却する行為や、破壊する行為、担保を設定する行為が挙げられますが、遺産を隠す行為が、「相続人のものにする」といった意図があると判断されれば、処分とみなされて相続放棄できなくなる可能性があります。
また、相続の放棄をした後であっても、遺産を隠匿して私にこれを消費すると、相続放棄は取り消されてしまいます(民法921条3号)。
遺産隠しがバレると、相続放棄は選択肢から外さなければなりません。
遺産隠しがなければ、被相続人の債権者は債権をより多く回収でき、遺産隠しに関わりのない相続人の遺産取得分はより増えたはずです。
そのため、被相続人の債権者や、遺産隠しに関わりのない相続人は損害賠償請求が可能になります。
隠し財産がバレると、過少申告加算税を課され、さらに仮装・隠蔽の疑いで、重加算税が課されます。
悪質と判断されれば、刑事罰(10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)を課されます。
相続税を減らすために遺産隠しをした結果、バレてしまい刑事罰をくらって人生めちゃくちゃでは、本も子もないですね。
変なところに頭を使わず、その分、正しい節税に頭を使いましょう。
遺産隠しは、必ずしもご自分の意図により発生するとは限りません。相続人の中には、被相続人の財産を持ち逃げする者がいないとも限りません。
たとえあなたが遺産を隠された側だったとしても、税務署は、被相続人の口座だけではなく、怪しい部分があれば、あなたの口座までくまなく調査します。
仮にご自分が隠していなくても、税務署に遺産隠しが見つかれば、重加算税や延滞税が、相続税を申告していない場合には無申告加算税が課されます。
そこで、相続においては遺産隠しを防止するための対策が必要なのです。
最後に、他の相続人に遺産を隠されないための対策をご紹介します。
遺産隠しが発生する原因の1つに、財産の全容を誰も把握していないことが挙げられます。
できれば生前に、ご自分にどのような財産があるのかを確認し、その内容を「財産目録」にまとめておくと良いでしょう。
予めどのような財産が存在していたのかが把握できれば、仮に遺産を隠されたとしても、そのことがすぐにわかります。
口座名義人がお亡くなりになったことを知ると、銀行はその口座を凍結します。
銀行が、新聞の訃報欄などから情報を得て口座を凍結することもありますが、一般には、相続人が銀行へ連絡することで口座が凍結されます。
裏を返せば、相続人が銀行へ連絡せず、銀行が口座名義人の死亡を知らない限り、被相続人のキャッシュカードとパスワードさえあれば、簡単にお金が引き出せてしまうのです。
親族がお亡くなりになられたら、できる限り早く口座を凍結させましょう。なお、この際に葬式費用を引き出したい場合は、その旨他の法定相続人などに了承をとって引き出すことをおすすめします。
ご自分の死後に、相続争いが起きる可能性が高い場合は、予め相続に強い弁護士と「財産管理契約」を結んで、第三者に管理してもらうことも一つの対策です。
同時に、遺言書でその弁護士を「遺言執行者」に指定しておくとさらに効果的です。
ここまで、税務署に遺産隠しがバレる理由や、バレるとどのようなペナルティ・罰があるのか、他の相続人に遺産を隠されないための対策を解説しました。
ご紹介した通り、税務署には税務調査の権限があり、一度目を付けられると、簡単に逃げおおせることはできません。
遺産を隠すより、事前に相続税に強い税理士に相談し、相続税対策をすることをお勧めします。