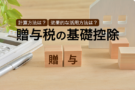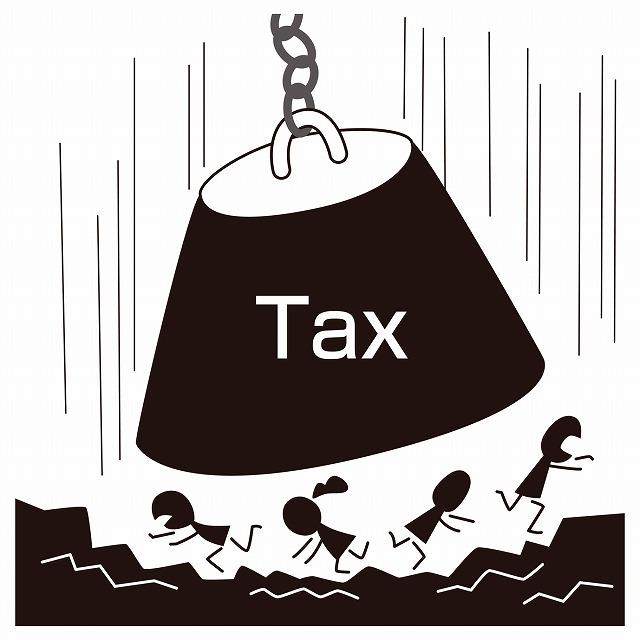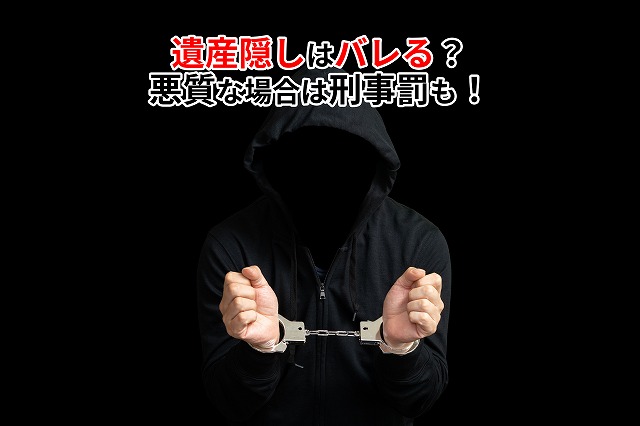贈与税の申告漏れ・申告忘れの実態と理由

誰かから贈与を受けたら受贈者は、その贈与金額が基礎控除額である110万円を超えていたら、贈与税を申告・納税しなければなりません。しかし、実際には贈与税の申告を必要だと認識しておらず、税務署から「申告漏れ」を指摘される人が多くいます。また、贈与税の申告が必要など認識はしていたが、ついうっかり忘れてしまったという「申告忘れ」も一部はあるかもしれません。ただ、外部からは「申告漏れ」と「申告忘れ」の区別はつけられないため、どちらも「申告漏れ」として数えられます。
どんな財産の申告漏れが発生しているのか?その実態をはじめ、勘違いしやすいポイントについて解説します。
目次
1.贈与税の申告漏れの実態
平成29年11月に国税庁が発表した「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」によると、国税庁では約90%の税務調査で贈与税の「申告漏れ」を指摘しています。そこで、この申告漏れの実態について、相続税の調査資料を基に解説していきます。
【外部サイト】国税庁:平成28事務年度における相続税の調査の状況について(付表5)贈与税に係る調査事績
1-1.税務調査の実施件数は?
平成28年度に実施された税務調査では、述べ3,722件の実地調査が行われました。そのうち、92.3%の3,434件が「申告漏れ」として指摘されています。この数字は毎年同じくらい高くて、税務調査が実施されると「9割以上」の確率で申告漏れが指摘されています。
このように高確率で申告漏れが指摘される理由には、まず税務署が「申告額が過少だと思う事案」と、「申告漏れが予想される事案」を中心に調査をしているからです。そのため、明らかに申告漏れだと分かる場合には、税務署から税務調査が入るのです。
1-2.申告漏れの財産の比率
平成28年度の贈与税の申告漏れで多かった財産の件数と、その比率は以下の通りです。
| 財産の種類 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 土地 | 129件 | 3.5% |
| 家屋 | 41件 | 1.1% |
| 有価証券 | 369件 | 9.9% |
| 現金・預貯金等 | 2,725件 | 73.1% |
| その他 | 463件 | 12.4% |
これを見ると圧倒的に「現金・預貯金等」の申告漏れが多いことが分かります。また、「有価証券」も含めると、約8割が金融資産によって構成されていることがわかります。こうした金融資産の「申告漏れ」が指摘されやすい理由としては、現金・預貯金などは税務署が把握しやすいからです。
一方、土地や家屋などの不動産は、基本的にその贈与額も多く、法務上の手続きも必要であるため、きちんと贈与税の申告手続きをすることが多いと考えられます。また、相続とは異なり、不動産を贈与する機会が少ないことも挙げられます。たいていの場合、親の名義で不動産を持ち続け、相続が発生してはじめて、子供に名義変更することが多いと思われます。
2.贈与税の申告が必要な金融資産とは?
平成28年度の金融資産の贈与における申告漏れ件数は、全体の83%にもなります。どのような金融資産の申告漏れが多く見られるのでしょうか。
2-1.申告漏れで最も多い「名義預金」
金融資産の贈与において、申告漏れで最も多いケースが「名義預金」によるものです。この名義預金とは、息子などの名義を借りて口座を作り、その口座に両親が預貯金をすることを言います。
これは一見すると、息子の名義で作った口座なのだから、息子の資産のように見えます。しかし、法律上はこの口座は両親のものです。なぜなら、この口座を実質的に管理・利用しているのは両親だからです。仮に息子の名義を使って口座を作っているとしても、両親の資産となります。
そして、この口座をそのまま名義変更して、息子のものとすると「贈与」としてみなされるのです。そのため、本来なら申告をしなければならないにもかかわらず、申告をしていないために申告漏れとして扱われてしまいます。
2-2.意外に間違える「親からの借入」
金融資産の贈与において、親から借金をする場合も申告漏れとして多いケースです。借金とは本来、貸主に対して返済をするものです。そのため、税務法上も贈与には当たりません。
しかし、この親からの借入を「免除」してもらう場合、贈与に当たります。本来返済する必要がある現金を譲り受けているからです。そのため、親からの借金を免除してもらった場合は贈与として申告をしなければなりません。
また、借入をしている場合は、通常は利息や催促などがあります。しかし、無利息で借入をしたり、親から返済の催促がない場合は、通常の借入としてではなく、「贈与」として見られることもあります。そのため、親からの借入と言っても、通常の金融機関と同等の借入条件で借金する必要があります。
このように親から借り入れており、それを将来返済するからと言って、申告しないでいると申告忘れとして見られる可能性があるのです。
3.贈与税の申告が必要な不動産とは?
平成28年度の不動産の相続における申告漏れ件数は、全体の4.6%です。金融資産に比べれば相当少ないですが、もし申告漏れとして税務署から指摘をされたら金額が大きいため大変です。そこで、不動産の申告漏れで、よく見られるケースについていくつかあげてみます。
3-1.親の名義を借りて、不動産を取得する
ローンを組めない息子や娘のために、親が金融機関から借入をして、親名義で不動産を取得することがあるでしょう。ただし、もしこの親名義で取得した不動産を、実質的に息子・娘が使用している場合、申告が必要な可能性があります。なぜなら、これは税務上、息子・娘のために不動産を買ってあげたと見られるからです。
仮に息子・娘が金融会社に返済をしている場合でも「贈与」に該当します。なぜなら、一時的には、親が住宅を買い与えたと判断されるからです。ただし、返済が終わった時に名義変更をしても、息子・娘は支払いをしていることから贈与税・相続税はかからないものとなっています。
子供が住宅ローンを組めないからといって、親が代わりに住宅ローンを組んで親の名義で不動産を購入することには要注意が必要です。むしろ、住宅用資金の非課税制度や相続時精算課税制度を活用し、子供に住宅購入のために必要な資金の一部を贈与したうえで、残りの金額を子供名義でローンを組み、子供名義で不動産を取得するのが得策と考えられます。
3-2.親から時価よりも安く不動産を買い取る
親から不動産を譲り受ける際、その価格は、路線価などで算出される時価に見合ったものでなければなりません。なぜなら、こうした時価よりも相当安くに不動産を買い取ると、それが贈与としてみなされてしまうからです。親から不動産を購入する場合でも、適正な価格にて買い取りをしなければならないのです。
また、金銭の受け渡しがなく不動産の名義が移動する場合も知っておく必要があります。こうした金銭の受け渡しがない場合は、間違いなく「贈与」に見られるため注意をしましょう。
そのほか、仮に時価よりも相当高く不動産を買い取った場合も「贈与」が発生します。これは適正価格よりも多くのお金を受け取ったということで、不動産をもともと持っていた人が贈与税を納める必要が生じます。
このように不動産の売買次第で、「贈与」に当たる可能性もあるため注意をしましょう。
まとめ
贈与税の実地調査は年間4,000件程度起きており、そのうち9割以上の確率で「申告漏れ」が指摘されています。この理由は「贈与だとは知らなかった」というケースが大半を占めているようです。どのようなやり取りをすると「贈与」に当たるのかを知り、贈与税が発生する場合は、適切に贈与税申告をするようにしましょう。