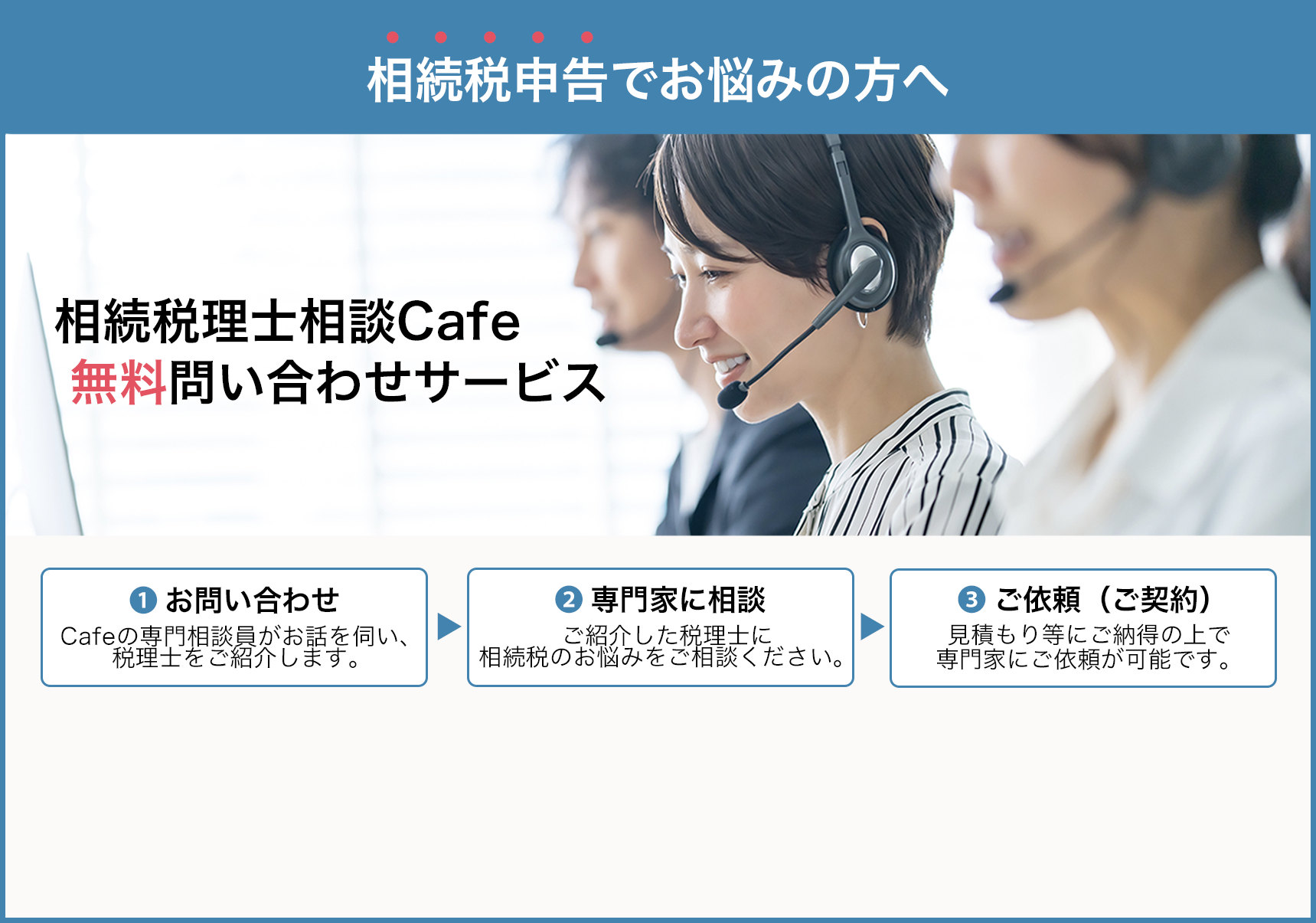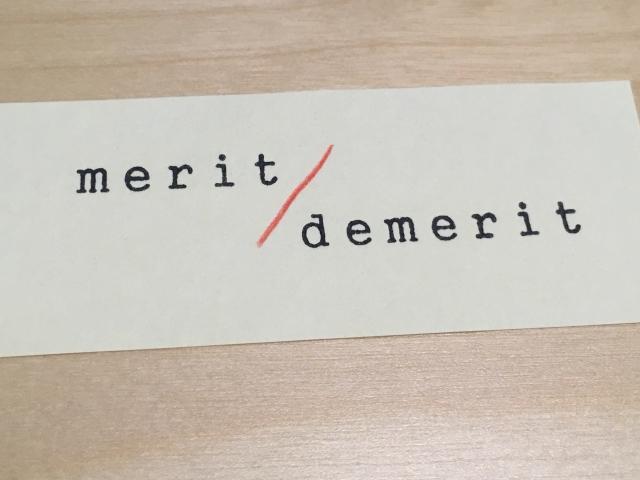相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が非課税ですが、相続時に精算されるので、まったく節税になりません。制度の仕…[続きを読む]
相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の併用、60歳未満でも可能

相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与は併用すると、3,500万円まで非課税(2022年12月時点)で贈与ができます。しかも、年齢制限がないという意外なメリットがあります。
それぞれの制度の概要と、併用したときの条件やメリット&デメリットについて解説します。
目次
1.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与したときは、2,500万円まで非課税になりますが、相続するときに過去に贈与した分を持ち戻して相続税がかかる制度です。
生前贈与したときに贈与税はかからなくても、相続時に相続税がかかりますので、節税にはなりませんが、税金を払うタイミングを遅らせることができます。
贈与者と受贈者の年齢条件
相続時精算課税制度を利用するには、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)にそれぞれ次の年齢条件があります。
- 贈与者(あげる人):贈与年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(父母または祖父母など)
- 受贈者(もらう人):贈与年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子供や孫など)
贈与者は60歳以上でないと、この制度を利用できないというのが、重要ポイントです。
注意点
相続時精算課税を利用するには、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。しかし、一度、提出してしまうと、暦年課税に戻ることができません。
暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税を選択すると、基礎控除を適用できなくなります。少額の贈与でも贈与税申告が必要になります。
2024年1月1日以降、税制改正で、110万円以下の贈与は特別に控除することができ、将来、相続財産に持ち戻して相続税がかかることもありません。
相続時精算課税制度の詳細は、次の記事をご覧ください。
2.住宅取得等資金贈与の非課税制度とは
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは、最大1,000万円(2022年12月時点)まで非課税で、住宅の購入や建築のために、贈与ができる制度です。
贈与者と受贈者の年齢条件
住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用するには、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)にそれぞれ次の条件があります。
- 贈与者(あげる人):直系尊属(父母または祖父母など)
- 受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子供や孫など)、所得2,000万円以下
非課税金額
非課税となる限度額は、住宅の種類によって異なり、次のようになります。
| 耐震、省エネ又は バリアフリーの住宅用家屋 | 左記以外の住宅 |
|---|---|
| 1,000万円 | 500万円 |
注意点
この制度を利用するには、贈与された住宅用資金の全額を、住宅の購入や建築のために使い、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに(どんなに遅くとも12月31日までに)、その住宅に住む必要があります。
また、この制度は期間限定であり、今のところ、2023年12月31日までです(延長される可能性はあります)。
住宅取得等資金贈与の非課税制度には、他にも様々な条件や注意点があります。詳細は、次の記事をご覧ください。
3.相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の併用
相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与は併用できます。
たとえば、省エネ住宅の建築のために、子供に4,000万円を贈与する場合、まず、非課税限度額1,000万円に住宅取得資金贈与を適用します。そして、残額3,000万円に相続時精算課税制度を適用します。2,500万円の特別控除額がありますので、残り500万円に20%をかけて、贈与税は100万円ですみます。
贈与者の年齢制限がない|60歳未満でも可能
基本的には、両方の条件を満たす必要がありますが、一つだけ条件が緩和されるのは、贈与者の年齢制限がないということです。
相続時精算課税制度では60歳以上という年齢制限がありますが、住宅取得等資金贈与と併用すると、この年齢制限がなくなり、60歳未満でも適用できます。
たとえば、50歳のとき、子供に住宅資金3,000万円を贈与したい場合、住宅取得資金贈与の非課税額は最大1,000万円ですので、通常だと残りの2,000万円に贈与税がかかり、約600万円近くも納税する必要があります。
ただし、相続時精算課税制度を利用できれば、全額、非課税で贈与できます(相続時には相続税がかかります)。
贈与した金額の中に、住宅取得のための資金が含まれていれば良いので、3,000万円の贈与のうち、500万円だけを住宅取得のためにあて、残りの2,500万円は別の用途にあてることも可能です。
4.相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の併用の注意点
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の両方を合わせれば、確かに多くの現預金を贈与することが可能ですが、いくつか注意点もあります。
小規模宅地等の特例を適用できなくなる
相続時精算課税制度を利用すると、相続が発生したとき、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
小規模宅地等の特例を利用すると、宅地で一定の条件を満たす場合、評価額を最大80%減額できますが、これを利用できないと、相続税が高額になるおそれもあります。
都心に自宅を所有していたり、宅地の面積が大きい場合には、相続時精算課税制度を選択する前に、一度、今の宅地の評価と相続税の試算をしておいたほうが良いかもしれません。
今後の贈与はすべて相続財産に加算されて相続税がかかる
相続時精算課税制度を一度利用すると、暦年課税に戻すことができません。今後の贈与は、将来、相続が発生したときに、すべて相続財産に加算されて相続税がかかります。
暦年課税であれば、少額の贈与で少しだけ贈与税を払って節税することも可能ですが、それができなくなりますので、ご注意ください。